 |
|||
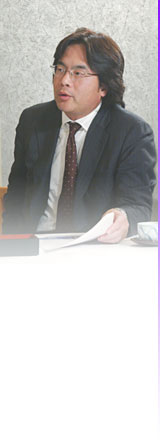 |
瀧内:最後に、これまでのお話を踏まえ、今後の胃癌化学療法に関して、是非これをやりたいという事やこういう方向に進むだろうという見解など、先生方一人一人に一言ずつご意見をいただきたいと思います。 小泉:やはり現在進行中のJCOG9912がkey studyだと思います。この試験の後、どういう展開が考えられるかというと、非常に難しく、次のstrategyがなかなか立てにくい。しかし、今までのお話を聞いてますと、やはり世界に並んでいかなければならないということは確かですね。そして、先ほど朴先生がおっしゃったような、ひとりの患者さんに対して、first lineからsecond、third lineまでの大きなarmで捉えて全治療をカバーしていくようなstrategyが、将来一番人にやさしい、生存を延ばしていく方法だと思います。ですから、それを目指して臨床試験の計画も立てていかなくてはならないと思います。 大津:1990年代に入ってCPT-11、S-1、taxaneと相次いで新薬が登場し、本当に手ごたえを感じました。先ほどJCOG9205とJCOG9912のMSTの差が話題になりましたが、まさにそれだけの実感があります。10年前の予測を超えて生存の延長が実現したとも言えます。これからも、治療戦略やregimenのmodificationについてやるべきことが色々ありますが、やはりインパクトが大きいのは新薬です。私自身はJCOG研究に加えて国立がんセンターという立場ですから、新薬の開発の部分を積極的にやってかなければいけないと思います。それも日本だけではなかなか難しい状況になっています。特に分子標的薬に関しては、外資系企業がものすごい勢いで開発を進めており、日本企業との圧倒的な差はいかんともし難い状況です。今まではCPT-11にしてもS-1にしても日本の開発品でしたから、我々が最初から手がけていましたが、今後はglobalの治験に入っていかざるを得ません。大腸癌のような海外との格差を生まないようにやっていきたいと思っています。 馬場:1990年以降、新規抗癌剤の登場によって胃癌でも生存の延長を目指した化学療法ができるようになったことが、非常に頼もしいことであります。しかし、それぞれの新規抗癌剤の位置づけ、first lineとして何を標準と考えたらよいのかなどについては、現在進行しているJCOG9912、あるいは企業主導のphase IIIの結果を待たなければならないと思っています。生存をendpointとして考えた場合には、first lineの標準が何かということだけではなく、今ある手持ちの薬剤をいかにうまく使って、second line、third lineと繋げていくことが大切になってくると思います。そしてsecond line、third lineまで考えたregimenでの試験も魅力あると思います。また、世界に通用するためには、いくら日本では胃癌症例が多いと言っても、世界とかけ離れたスタンスではなかなか認めてもらえませんので、アジアを取り込んだ国際共同の臨床試験を考えていくべきだと思います。 小寺:medical oncologistの先生方を前に進行再発胃癌の展望を云々するのは僭越ですから、ここでは補助化学療法についてお話しいたします。T3症例の予後は良好とは言えず、集学的治療が必要と言いたいところですが、術後補助化学療法で治療成績を改善するのは難しいというのが今日までの臨床試験の結果の大筋です。胃癌と他の癌腫との大きな違いは、手術のみで既に消化器毒性が起きている点で、胃癌根治術後の化学療法のコンプライアンスは良好とは言えず、多少なりとも消化器毒性を有する薬剤を使う場合には問題になります。ですから、今後の方向としては、術後ではなく患者が元気なときに徹底的に行えるneo-adjuvantにbreakthroughがあるのではないかと考えています。そのためにも奏効率が高い、特にCR率の高いregimenを是非作っていきたいと思っています。日本は、neo-adjuvantの臨床試験に関してはまだ黎明期で、CPT-11+CDDPを経て現在S-1+CDDPが評価されようとしていますが、phase IIIはまだこれからという状況です。手術自体の成績がよいものですから、最近まではあえてやられてこなかったということなのでしょうが、今後はそうした方向で考えたいと思っています。 朴:僕は単純にJCOG9912をきちんと終わらせたいと思います。とにかく背骨といいますか、礎を作って次の展開ができるようなものを早期に、後3年で決着をつけるのが今の僕自身に与えられている一番の課題だと思います。 瀧内:それが一番大事で、胃癌化学療法を考える上でのベースになるということですね。 朴:先ほどPFSの話題が出てきましたが、5-FUに比べてPFSの長い薬はいくらでもありますが、結局生存は延びていません。ではPFSが最も長い治療法はどれだといわれると、ベースも何もありません。毒性のことも考慮すべきですが、文句のつけられないようなきちっとしたregimenをひとつ作らない限りは、次の展開を考えられるはずはありません。FDAが大腸癌はPFSで評価してもいいが、胃癌はOSでなければと言っているのはそこです。 瀧内:なるほど。そのkeyになるのがJCOG9912だということですね。そのJCOG9912の中間解析結果に代表されるように、胃癌の化学療法が生存において明らかに進歩していることがわかりました。今後胃癌の領域では日本が世界のリーダーとしてやっていかないといけないということを考えますと、将来的には国際間の共同の臨床試験を視野に入れていかなければならないと言うこともよくわかりました。是非、先生方が中心となり、日本の胃癌の治療をさらに発展させていただき、世界にアピールできるようなデータを発信していただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 |
||
| 目次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |||