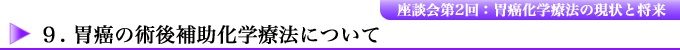 |
|||
 |
瀧内:今日は消化器外科の第一線の小寺先生、馬場先生に参加していただいておりますが、補助化学療法について、日本や欧米の現状をお話していただきたいと思います。 小寺:術後補助化学療法に関しては、JCOG9206という、手術単独をcontrolとした試験が組まれましたが、主にT2程度のものを対象にしたものJCOG9206-1とT3以上のものを対象にしたJCOG9206-2があり、いずれも1992年頃から症例を集積してきたものです。JCOG9206-1については示唆に富んだ生存曲線になったものの、有意差はつきませんでした。当時は試験デザインに関しても未熟で、少ない症例数で15%という大きな差をみようとした事に無理があったと思います。regimenはmitomycin C+5-FU+Ara-C(MFC)の後、経口の5-FUを投与するもので、非常に毒性が少ないものですから、僅差であっても有意な差であれば価値があったかもしれないと今では考えています。もう一つのJCOG9206-2は、漿膜浸潤陽性例に対するもので、当時としては新しいCDDPの腹腔内投与を含む強力なCDDP+5-FUと、その後にUFTを投与するregimenでした。この試験結果がつい最近出たのですが、見事に期待を裏切られました。これら二つの結果をみると、手術がしっかりしているという事があるのだ思いますが、欧米と比べると非常に差が出にくい状況だと思います。現在、S-1 vs 手術単独の試験が行われていますが、この結果にも少々不安を感じています。 馬場:日本には補助化学療法に関してかなり長い歴史があります。しかし、meta-analysisではその有用性が示されているものの、単一の試験で有意差を出したものがほとんどないのが現状です。ただ、本当に補助化学療法の効果がないのではなく、試験のデザインによって差が出ないのかもしれません。例えば乳癌の補助化学療法をみても、数%の差を出すために1000例単位の症例数の蓄積をして初めて有意差を出していますから、試験のデザイン、特に症例数はひとつの課題かもしれません。胃癌における補助化学療法の有用性を大規模な試験で評価するという意味では、現在行われている企業主導のACTS-GC 瀧内:ということは、ACTS-GCの結果がでるまでは、日本の胃癌補助化学療法における臨床試験のスタンスとしては手術単独をcontrolに置かざるを得ないというわけですね。また欧米には、補助化学療法にradiationを併用するというDr.MacDonaldが報告したデータ(New England Journal of Medicine Vol.345:725-730,1999)がありますが、やはりあの報告は、日本の外科の先生方には受け入れ難いデータと考えてよろしいですね。 馬場:Dr.MacDonaldの報告では、いわゆるほとんどリンパ節郭清をしていないわけです。D0が54%、D1が36%ですから、一群までのリンパ節郭清に留まるのが9割です。従って、手術の質が日本とは非常にかけ離れたレベルであるとしか言えません。化学放射線療法を行って手術単独よりも有意に優れていたと言っても、放射線を照射することで、私達が通常行っている手術による局所コントロールの代替をしたと解釈するしかありません。アメリカで標準的な位置づけを獲得したからといって、日本でそれをそのまま導入することはありえないですね。 小寺:さらに、再発形式を解析しますと、化学放射線療法で抑えられたのは局所再発であって、遠隔転移の頻度は2群間で同等です。まさに、放射線照射がわが国におけるリンパ節郭清の代わりをしていることを示唆する結果だと思います。 |
||
| 目次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |||