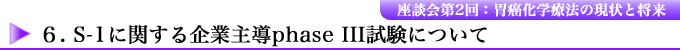 |
|||
 |
瀧内:S-1のさまざまな併用療法のどれもが50%を超す奏効率で、MSTも非常によいということですから、併用対象の薬剤のメーカーが種々のphase IIIを企画していると聞いています。こうした中では医師主導型治験もなかなかやりにくい状況にあると思いますが、今後、胃癌領域で、大きな比較試験をやっていくことができるでしょうか。S-1をとりまく環境にも大きな変化が出てきていますが、いわゆる医師主導型の臨床試験の最先端におられる朴先生、この状況をどうご覧になっていますか。 朴:企業主導型の臨床試験に関しては、いくつも並んで走っていますから、お互いに食い合ってつぶれなければ、と心配しています。ただ、実際、企業主導型の臨床試験によって、試験参加施設の裾野が広がったことは事実だと思います。企業主導型、企業の市販後臨床試験は求心力があり、経済的にも余裕があるので、臨床試験を行う施設を発掘し広げることができます。そうする事で、それぞれのグループが二つや三つの臨床試験をお互いにカバーし合いながら、並行して進めていけるのが最もよい形だと思います。実は、データを見せていただいたのですが、「こんなにがんばっているんだ」と、目に付いた病院がたくさんありました。そういう意味では、企業の試験に何も言うことはありません。ただ、もしかしたらお互いを食い合っているかもしれないという気がしますが、そこは生みの苦しみでないかなと思います。 小泉:臨床試験に関しては、これまでJCOGが作ってきた歴史を十分理解した上でstrategyを立てる必要があると思います。標準的な治療が決まっていないとはいえ、やはり無駄な試験に症例を費やすのは、やはりやってはいけない事だと思います。ですから、次々にいろいろな臨床試験が立ち上がってくるのに対し、それをコントロールする機関が必要だと思いますが、やはり学会主導でやるべきです。胃癌学会の中に、日本の化学療法を考える委員会のようなものを作り、企業の方々にも入っていただいて、臨床試験の遂行に関し、十分な体制を取れるように議論していったらよいのではないかと、思います。 瀧内:非常に貴重なご提言だと思いますが、大津先生は、phase IIIが常に企業主導で進んでいることに関しては、いかが考えられますか。 大津:最初は、本当に大丈夫かなという心配をしていましたが、実際行われてみるといずれもしっかりしていて、日本もきちんとphase IIIをできるようになった、という進歩を実感しました。しかしながら問題なのは、S-1自体の評価がまだはっきりしていない段階で、S-1をcontrol armする試験も動いている事と、もうひとつは国内での臨床試験だけでは限界があるのではないかということです。大腸癌では既にはっきりしていますが、海外との共同試験を進めないと勝負できません。胃癌においては、欧米は症例が少ないですから、今後アジアの国々との共同研究が重要になってくると思います。特に韓国など、患者さんも医療制度も非常に似ているところがありますから、どのように共同で臨床試験を行っていくか、次のステップとして考えていかなくてはならないと感じています。 |
||
| 目次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |||