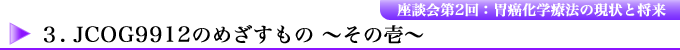 |
|||
 |
瀧内:1990年代の後半にいろいろな新薬が登場し、JCOGでもそれらの新薬を組み入れたphase IIIが新たに始まったわけですが、新しいphase IIIであるJCOG9912について、朴先生、簡単にそのコンセプトをご紹介ください。 朴:1990年代後半にCPT-11とS-1が開発された際にphase Iからphase IIとすべて携わってきましたが、その奏効率の高さ、切れ味の鋭さに大変興奮しました。しかも、両薬剤ともに日本で開発された薬だということでしたし。JCOG9205では結局また5-FUがreference armとして生き残ったわけですが、今度こそ5-FU単独に勝てるのではないかというのがJCOG9912に託されている思いです。その検証内容は、CPT-11+CDDPについては毒性が高いですから、生存において有意であるかどうか、S-1については経口剤というメリットがありますので、5-FU持続静注に対して非劣性であるかどうかの検討です。2000年の後半にスタートしていますが、2007年には何とか結果を出したいと考えています。 ●CPT-11+CDDPについて 瀧内:小泉先生、JCOG9912の試験armのひとつであるCPT-11+CDDPの併用ですが、この組み合わせの特徴はどのようなものなのでしょうか。 小泉:私もJCOG9912に参加させていただきまして、11例の内3例か4例がCPT-11+CDDPに入り、確かに非常に奏効しました。しかし、やはり非常に毒性が強く、何人かの患者さんがクリーンルームに入ってしまうという状況でした。もちろん治療関連死につながるようなことはなく、きちっと診れば決してやれないことはありません。そして継続性も比較的ありますので、長い生存を得ることができ、非常によい感触のregimenなのです。ただ入院期間が長くなってしまうという問題があります。外来化学療法に変わりつつある現在の医療事情から、外来でCPT-11+CDDPができないかという話があり、栗原稔先生や瀧内比呂也先生、佐藤温先生等とグループをつくって、CDDPをday 1とday 15に30mm/m2ずつに分けて投与するbi-weekly投与を検討しました。肺癌の試験等から、CDDPは30mm/m2であれば日帰りで十分ハイドレーションも可能で、後に腎毒性を残さないということがわかっていましたので、それをベースにし、CPT-11のrecommended dose(RD)を60mm/m2と設定しました。primary endpointは奏効率ですが、大きな目標として、5-FU failureの後のsecond lineとして、外来でCPT-11+CDDP投与ができることを考えて検討しています。現在、実際の臨床で使用していますが、非常に使いやすいregimenです。CPT-11も30mm/m2から効果を認めますので、CDDPとの組み合わせの場合、必ずしもCPT-11の投与量を多くしなくてもいけると考えています。 瀧内:5-FU based regimenがfirst-lineで使われることが多いのでsecond lineに使われているわけですが、first lineでも十分使えるということですね。 小泉:はい、first lineでは53.3%の奏効率があります。 瀧内:これは欧米の実地臨床でも好まれて使われているregimenですが、我々がJCOGの登録症例でこのregimenに当たった際の印象でも、toxicity controlさえできれば、意外に長期生存している方が多いという感触があります。first lineとして生き残る可能性が十分あると思いますが、いかがですか。 朴:せっかくphase IIIを組みましたので、有意差をつけて終わりたいと思っています。Dr.AjaniもCPT-11+CDDPについてほとんど同じ結果を発表していますし、両薬剤ともに欧米でも大腸癌でよく使われていますので、JCOG9912でCPT-11+CDDPが勝てば、JCOG9912の結果は海外でも受け入れられると思います。そう考えますと、是非CPT-11+CDDPに勝ってほしいという気持ちが強いですね。 瀧内:試験結果が非常に楽しみだということですね。外科の先生からみた時に、この併用療法をどのようにお考えですか。 小寺:私共は、JCOG0001という胃がん外科グループの試験で、このregimenをneoadjuvant settingで使用するphase IIを経験しました。 瀧内:bulky N2リンパ節転移の症例ですね。 小寺:治療関連死(treatment related death:TRD)が5%以内を目標としていたので、集積目標60例中3例以上出た場合には試験中止とされていたのですが、集積終了寸前に3例目のTRDが出て、その時点で打ち切りとなりました。もっとも、TRDの内1例は高度な食道浸潤で右開胸開腹を要した胃癌としては非常に特殊な症例でしたし、他の2例は化学療法の段階で骨髄抑制を主体とする有害反応で亡くなっており、このregimenによる術前化学療法の後外科手術を行うことそのもののリスクは感じておりません。ただ、術前化学療法ですので、施設によって外科医が行ったり、medical oncologistが行ったりというばらつきがあり、この点が本regimenを開発されたoncologistの先生方には不本意に感じられる点かもしれません。 瀧内:これはやはりmedical oncologistのためのregimenとお考えですか。 小寺:必ずしもそうは思いたくはないのですが、非常に注意して行う必要のあるregimenではあって、化学療法に十分に精通した医師が行う必要はあると思います。今までわが国で普通に行われてきた化学療法と同じ感覚で行うべきものではないということです。 大津:先生方のお話はよくわかるのですが、併用のregimenを組む際には、標準的なスケジュールを組み合わせるのが本来のやり方だと思います。我々が行っているのも、標準療法どおしを組み合わせ、それをそのままphase IIIまで継続しているわけです。それぞれの施設やグループがregimenをmodifyしていくことはあるでしょうが、そのすべてをphase IIIで検証していくのは現実に不可能ではないかと思います。確かにbi-weeklyのCPT-11+CDDPでtoxicityが下がるのもわかりますが、いったいどれほどの差なのかということを評価するにはRCTが必要になってしまうということです。細かいmodificationを重ねていっても、以前のlow dose FPと同じように、結局何もわからないままということになるだけです。toxicityが高いといいますが、JCOG9912のデータをみても、CPT-11+CDDPのTRDは約2%、JCOG9205の際の5-FU+CDDPではTRDは約4%です。他の5-FU+CDDPでの報告もほぼ同等です。海外のデータをみても、格別CPT-11+CDDPのTRDが突出して高いわけではないと思います。CPT-11+CDDPという大きな枠組みの中で、phase IIIの最後まできちんと評価していくべきだと思います。 瀧内:JCOG9912の結果が出れば、CPT-11+CDDPの位置づけもわかるということですね。 小泉:CPT-11+CDDPとS-1の比較はしないということですが、例えば5-FUにCPT-11+CDDPが勝ち、またS-1が5-FUに対して非劣性となった場合に、この試験の結論としてどのようなregimenを推奨することになるのでしょうか。 朴:その場合はダブルスタンダードという結論になります。製薬会社が行っているS-1 vs S-1+CDDPの試験の結果でS-1+CDDPがよいとなれば、次にCPT-11+CDDP vs S-1+CDDPという比較試験も考えられるかもしれません。 小泉:次の臨床試験を組む際のreference armをどちらと考えるのですか。 大津:直接の比較はしませんが、CPT-11+CDDPとS-1の生存曲線がどうなっているかは判断に影響を与えると思います。CPT-11+CDDP の方がかなり上に行っているということであれば、reference armはCPT-11+CDDPになるでしょうし、そうでもなければS-1になるでしょう。小泉先生が行っている試験の結果も影響を与えると思いますし、状況によると思います。 朴:もし新薬がS-1と組んでphase IIでよい成績を上げてくれば、S-1をcontrol armとして比較する試験になります。 瀧内:今後の実地医療のことを考えたら、使いやすいregimen、コントロールしやすい治療法をphase IIIでは採用してほしいと思いますね。 ●S-1について 瀧内:JCOG9912のもう一方のarmでありますS-1について、外科のお立場からお考えをお聞きできますか。 馬場:S-1は、発売以来日本国内で広く使われていますが、最初に最も注目されたのは、単剤での奏効率の高さです。後期phase IIでのデータは奏効率46.5%、MST 244日、1年生存率36%、2年生存率16.5%ということで、単剤での奏効率の高さと、2年生存率が10%を超えていたという二点で注目されました。また、進行再発胃癌の中で腹膜播種を来たしやすく、最も治療に難渋してきた低分化型腺癌に対し、比較的効果がよかったという点も注目すべき点だったと思います。先程来話題になっているCPT-11+CDDPも効果があるのは分化型ですから、低分化型腺癌に対して比較的切れ味がよく、長期生存が得られるという点は大きいと思います。ただ最終的には、phase IIIであるJCOG9912の結果を待たないと、S-1の位置付けを結論付けることはできませんし、企業主導のいくつかのphase IIIの結果も待って、評価すべきものと思います。しかし、入院から外来へと化学療法がシフトしている現状を考えると、実際の医療現場で非常に使いやすい薬剤であることは間違いありません。後はこれをどう生かしていくかだと思います。 瀧内:外科の先生方は、実際の医療現場において、S-1を標準治療として使っていることが多いだろうということですね。以前のlow dose FPがS-1にシフトしていったということでしょうか。 馬場:そうだろうと思います。 大津:S-1の特徴として付け加えるとすれば、原発巣に効くというか、食事が摂れるようになる等、患者さんの症状がよくなりますよね。使いやすいですし。日本でこれだけ使用されているのも頷けるところです。我々が治験を行った際も大変効果が高く驚きました。ただ問題になるとすれば、海外での承認申請用試験が遅れ、普及がうまくいっていない点です。 |
||
| 目次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |||