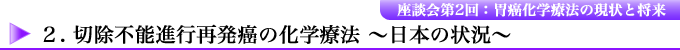 |
|||
 |
瀧内:欧米では、1990年代からDCFやEAPに代表されるような、効果は高いが有害事象も強いregimenが研究されてきたわけですが、日本についてはどうなのでしょうか。 小泉:海外と比べると日本の進行胃癌に対する化学療法は大分遅れておりました。JCOGで栗原稔先生のグループがtegafur+mitomycin C vs UFT+mitomycin Cでrandomized controlled trial(RCT)を行ったのが、臨床研究としては最初になると思います(JCOG8501 Jpn J Cancer Res.82:613-620,1991)。この試験の結果は、UFT+mitomycin Cが奏効率では勝るもののmedian survival time(MST)では有意差なしというものでした。その後いくつかの治療法の検討を経て、JCOG9205で5-FU持続静注、5-FU+CDDP(FP)、UFT+mitomycin C(UFTM)の三者比較試験が行われ、UFTMがtoxicityにより中断された後、FPと5-FUではMSTに有意差を認めないという結果が得られています。ただ、progression free survival(PFS)においてはFPが優れており、toxicityもFPの方が高かったとのことです。JCOGではこの結果から5-FU単独をreference armと考え、次のJCOG9912で、S-1、irinotecan(CPT-11)+CDDPを5-FU単独と比較する試験を行っています。 瀧内:JCOG9205は5-FUをcontrol armにおいて比較試験が行われています。1990年代の欧米には、NCCTGのトライアルを除いて5-FUをcontrol armにした臨床試験が全くなかったわけですから、ある意味、日本では違ったスタンスで臨床試験が展開されており、それが現時点でも続いているということですね。Dr.Ajani達はJCOG9205の結果をみて、FPのPFSが有意に延びていたので、今後FPも臨床試験のcontrol armにすべきだとコメントしていたようですが、大津先生、その点に関してはいかがでしょうか。 大津:JCOG9205の重要なポイントは、日本で元々ポピュラーであったUFTMと、海外で盛んに行われていたFPを組み入れたということです。そこに5-FU単独が入ったのは、それ以前に流行していたEAPに治療関連死が10%も出てしまい、世界的にもintensiveな治療が疑問視されていたためです。結果で驚いたのは、5-FU単独よりUFTMの生存曲線が下回ったことです。最終的には生存に差がありませんでしたが、中間解析の段階では有意差がつくところまできていましたので、留意すべきことと認識しています。5-FU単独と5-FU+CDDPとの比較は、小泉先生が言われたように、PFSではFPが有意に優れていましたが、MSTでは全く同様でしたから、control armを5-FU単独とするのか、5-FU+CDDPとするのかについて、JCOGの中で、大議論になりました。最終的には5-FU単独をcontrol armとしたわけですが、primary endpointがoverall survival(OS)だったため、全体の生存が延びないのであれば、有害事象の少ない方を選択すべきだろうというのが理由です。それに対して海外からも批判があることは重々分かっております。5-FU+CDDPを否定するわけではないわけですが、生存が延びないと意味がないわけです。PFSが5-FU単独で1.9ヵ月、FPでは3.9ヵ月と、有意差がついていたものの、結局MSTはどちらも7ヵ月と変わらなかったのです。これをどう解釈するか、それぞれの臨床医の価値観によるのではないかと思います。 瀧内:PFSでは差があったものの、全体の生存では差が開かなかったというのは、非常に面白い事実ですが、何故そのようなこととなったのでしょうか。 朴:実際、自分の登録した患者さんが5-FU単独群に割り付けられ、主治医としては何としてもその人を1年間生かしてあげたいという気持ちで治療にかかるわけです。今はJCOG9205の時代と違い、second line、third lineが充実していてOSも1年くらいになりますので難しくはないのです。結局、FPのPFSは5-FU単独より長かったものの、OSに与えるだけのインパクトがなかったということだと思います。胃癌の化学療法でPFSにどのくらい差がつけばOSにインパクトが出るのか、僕達が知らないだけかもしれません。second lineにCDDPをもってくれば、first lineの差を埋める事ができるのだと思います。ASCO2004で結腸直腸癌のadjuvant療法で、3年disease free survival(DFS)が5年OSと相関するという報告(ASCO2004 #3502)がありましたが、胃癌においてはそういう話は全くありません。PFSに対する思い入れが強すぎるのかもしれません。 小泉:私もこの試験に加わっていましたが、当時、5-HT3拮抗薬がなかった時代ですから、CDDPが5日間に分割されて20mg/m2入ると、激しい消化器毒性が出ていました。こうした厳しい条件での臨床試験で、CDDPの併用効果に生存の延長がないと決めつけてよかったのだろうかと思うのです。海外では、欧米のDCF、ECF、韓国のFPなど、いずれのregimenにもCDDPはkey drugとして入っています。この世界の流れから日本だけ外れてよかったのか、その判断に一つの大きな日本の分岐点があったのではないでしょうか。 大津:JCOG9205のFPのデータは、toxicityに関して海外の標準投与量の場合とほとんど変わりません。総投与量ではほとんど同じですからね。また、second line等の影響に関して、どれだけcross overしているかをみましたが、ほとんど変わりはないと思います。5-FU単独の後のsecond lineとしてのFPの効果も検討しましたが、ほとんど影響していませんでした。小泉先生のご指摘については同感ですし、だからこそ調べてみたのですが、データからは差を見出せなかったというのが実情です。 瀧内:すると、5-FUにCDDPを上乗せする効果には疑問があるとお考えなのですか。 大津:いいえ、CDDPの上乗せを否定する成績ではありません。responseを狙うべき局面ではFPを行うべきでしょう。しかし、あくまでOSは、MSTのみならず1、2年生存率も5-FUと変わらないのですから、今後のcontrol armとしては5-FU単独をreference armに選択したということです。 瀧内:外科の立場から、FP、特にCDDPの位置づけをどのようにお考えでしょうか。 馬場:CDDPは胃癌化学療法のkey drugであり、CDDPを上乗せすることで奏効率が上がるのは間違いありません。ただそれに伴って毒性も上乗せになっており、生存を延長させることができなかったのがこれまでの結果です。日本では、独自の使い方として低用量の少量分割投与(low dose FP)という治療法が広く行われてきています。これは毒性を軽減することで長期の治療継続を可能にし、それが長期生存につながるのではないかという考えに基づいているものです。ただevidenceがありませんので、low dose FPには懐疑的にならざるを得ません。FP療法は奏効率が確かに高くなりますので、外科の立場で言えば術前化学療法等でうまく使う方法があると考えています。 瀧内:現在5-FUの投与は、持続静注で行われる傾向にあると思いますが、それが経口剤のS-1に置き換わり、low dose FPもS-1+CDDPというregimenに大きく移行してる状況と考えてよいのでしょうか。 小寺:low dose FPは5-FUを持続静注しなければなりませんから、外来では不可能です。結局何週間も入院することになり、患者さんにも医療側にも大きな負担がかかります。その上、何サイクル継続すればよいのか、いつまでも入院しているわけにもいきませんので、その後はどうすればよいのかなどという点で結論が出ていません。一方、S-1は経口剤ですから外来投与が可能であり、その他の問題もすべて解決してしまったわけです。事実上これがかつてのlow dose FPに置き換わっていると言えるでしょう。ただし、CDDPを上乗せするかどうかは本来は別問題です。代表的な例としては仲田文造先生(大阪市大・腫瘍外科)が発表されているS-1にlow dose CDDPを併用するregimenがあり、phase Iが終了し、良好な奏効率が出ています。もちろん他のregimenと比較され、評価される段階にはありませんが、low dose CDDPの併用そのものはこうした形で細々と生き残っている部分もあるわけです。ただ、それが実地臨床で容易に使えるかと言うと、週5日間外来に来ていただきCDDPの投与ができる施設はかなり限られているのが実情でしょう。よいか悪いかは別にして、実地医療として行うには無理があると考えています。 |
||
| 目次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |||