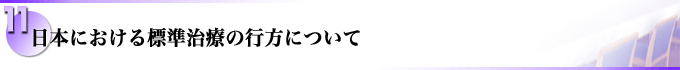 |
||
瀧内:先生方のお話を伺っていますと、日本と海外との間の差が今後埋まっていくのではないかと期待できそうですが、実際に、朴先生、大腸癌の場合には、日本における標準的治療というものは、海外のevidenceに基づいていくべきであるという理解でよろしいですか? 朴:今現在、IFLをfirst lineにもってきていますけども、実際はそれよりもFOLFOXがいいと思っています。僕達が日頃行なっているよりも優れた治療を欧米でやっていることが、非常に悔しいです。日本の標準治療という言葉自体がおかしいわけで、世界の標準治療はひとつのはずです。それを日本人もやるべきだと思います。世界で一番良いとされているものが標準治療であるべきです。doseの多少はあるでしょうけども、標準治療というのは、世界で共通なものであるべきだと思います。 瀧内:実際の医療現場の多くの先生方は、海外のevidenceは海外のevidence、日本は日本と分けて考えておられると思うんですよね、その溝を、うまく埋め合わせが出来ればと僕自身も思うんですけれども。 大津:今の日本の現状では、実際に大腸癌の化学療法を担っていらっしゃるのは外科の先生であって、内科医がそこに関与できていないことが、一番の問題だと思います。かつて5-FUしかない時代は、ある意味、外科手術をしながらでもできたと思うのですが、CPT-11、L-OHP、bevacizumab、cetuximab等など、次々と出てきますと、これはもう、そう簡単ににできる範囲ではないと思います。私自身でも、消化管癌、食道癌、胃癌、大腸癌をやって、すべての進歩になかなかついていけない状況になっていますので、そこを改善しないとならないのではないでしょうか。内科のoncologistが増えてきて、徐々にですけど、変わってきているんじゃないかというふうに思います。 藤井:oncologistが増えて、早くそうなってほしいと思いますが、外科の方でも胃癌の専門家、大腸癌の専門家と分かれており、胃癌の専門家の先生は、胃癌の化学療法しか知らないし、大腸癌の先生は大腸癌の化学療法しか知らないけれども、そこの専門領域のトップの人達は、かなり詳しい人が多い。内科の先生たちも勉強してもらって、一生懸命oncologistを増やしてもらいたいですね。今、外科医が全部化学療法から手を引いたら、内科医だけではもう忙しくて診ていられないわけだから。
外科医は手術だけすればいいようにしてもらいたいんだけど。(笑) 瀧内:内科、外科、それぞれの立場から大腸癌化学療法における日本のoncologistの現状に対する貴重なご意見をいただいたと思うんですが、interventional radiologyを専門とされている荒井先生から何か御提言、一言ありませんでしょうか? 荒井:Radiation oncologyはやってなくて、一応Interventional radiologistのつもりなのですが。(笑) 朴:静岡がんセンターに移ってIVRの大事さを非常に感じています。画像診断の先生から、骨盤内再発で「痛い、痛い」と言っておられる患者さんに対して、ラジオ波で腫瘍を焼灼するなど、我々が思いもつかないような治療法が提案されています。大腸癌は化学療法が効かなくなってからが長いですから、延命のみではなく、症状コントロールなどの、患者さんのマネージメントという点においても、IVRに対する期待は大きいと思います。 大津:我々もそういう意味では、本来内視鏡が専門で、どちらが片手間かわからないですが(笑)。逆に言えば、内視鏡にしてもそうですし、IVRにしても、もちろん手術はそうですけれども、そうした技術は日本は非常に得意です。そこに客観性を与えるような評価の仕方を、我々が知らなかったということですよ。逆にそうした領域の臨床試験はこれからですから、そこでは逆に日本が主導的に作っていける部分があるのではないかと思います。抗癌剤の臨床開発については、海外の国際学会に行くたびに落胆し、なんでこんなに遅れていくんだと思いますが、逆に言うと、研究者の力だけではなく、厚生労働省、製薬企業も一緒になって、患者さんにいかに早く良いものを還元するかを考えて、なんとか追いつくようにしなければならないんじゃないかと思いますね。 瀧内:それは可能だと? 大津:最近、だんだん風向きが変わってきています。治験の基盤整備もかなり確立されてきていると思いますので、数年から5年ぐらいはかかるでしょうけど、今の遅れはかなり取り戻せるだろうと思います。将来的には、日本での開発ではなくて、海外と同時に開発しましょうと、そこで日本が主導的な立場を取っていくと、試験のqualityで言えば決して日本が遅れているわけではないですから、ちゃんとやっていけば、必ずそういう主導的な立場に立てるのではないかと思います。 瀧内:ありがとうございました。本日4人の先生方からのご指摘を私なりにまとめてみますと、欧米との格差が大きいと言われていた大腸癌化学療法の領域ですが、近い将来その格差も埋まっていく可能性が高いのではないか。そして将来的には日本も主導権を握った大腸癌のinternational
studyが組める可能性までもあるのではないかという力強いお言葉までいただきました。是非本日出席いただきました先生方が中心となって、大腸癌化学療法の分野においても日本が世界的な役割をはたしていけるようになってほしいと思います。本日は本当にありがとうございました。 |
||
|
||
| 目次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | ||
