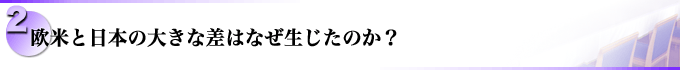瀧内:まず大腸癌化学療法の総論について、それぞれの立場から貴重なご意見を各先生方からいただいたのですが、海外で使える薬剤と日本で使える薬剤とで、現状大きな格差があるわけです。このことが大腸癌化学療法の治療戦略を考える上でさまざまな制約となってきます。実際日本の現状は、日本独自の戦略を考えていかなければならないのか、それとも海外のevidenceを積極的に取り入れていかなければならないのか、非常に難しい現状だと思うのですが、海外と日本の大腸癌化学療法の現状に、どうしてこのような大きな差異が生まれたのでしょうか。大津先生、どのように考えられますか。
大津:これだけの差異が生まれているということは、いろいろな要因が複雑に絡まっていると思うのですが、整理すると大きく4つになります。
ひとつは、疾患自体、つまり大腸癌の発生頻度は欧米の方が圧倒的に高く、日本では患者が少ないために治験の進行スピードが遅いことです。
2番目は我々研究者側の努力が足りない。日本の大腸癌化学療法の大半を、外科の先生が行っているのが現状で、内科医のパワーが足りず、承認申請試験がはかどらないということが過去にありました。
3番目は行政的な側面。承認申請のシステムが海外と異なっていることですが、大きな要素として、GCP基準の改正が1997年に行われ、承認申請試験のqualityが急激に厳しくなったものの、それへの対応が遅れたことです。要は、グローバルスタンダードの承認申請試験のqualityが、当時の日本ではできなかったことです。ようやく今、いろいろな施設で承認申請試験のqualityに耐えうるシステムができあがってきています。
最後の点は製薬企業側の問題です。GCPの改正があったことで、企業側も日本での治験をやらず、海外治験に流れたところが多かったという点です。
企業の方の話を聞くと、グローバルの治験をやっていく上で、どうしても日本は取り残される、それは様々な問題、申請のシステムの問題や、費用の問題、結局のところ、語学の壁も大きな要素ではないかとも思うのですが。ただ、現在はいろいろな問題点も改善されてきていますので、近い将来には追いつくだろうと私自身は思っております。
瀧内:大津先生は、海外に日本も追いつきつつあると、言われましたが、朴先生はどう考えますか。
朴:追いつくかと言われれば、僕はまだまだ難しいと思います。企業の開発戦略からみると、欧州だけ、米国だけで試験が組めるのに、わざわざ費用をかけて日本にも参加させて試験を組むことは効率的ではないと思われるでしょうね。日本が取り残されるのはやむを得ないことになるのかな、と思います。
欧米と日本との差を考えるときに、韓国の状況と比較をするとわかりやすと思います。韓国では、行政が海外のエビデンスを簡単に全部受け入れ、薬剤を市場に出します。こういう安易なことでいいのか悪いのかわかりませんが、Medical
oncologistの数が多く、薬さえ出せば安心して使ってくれる土壌があるのです。これに対し、薬剤が承認されてもどんな使われ方をされるかわからない、もしくは、1%程度の治癒関連死亡が、「何人死にました」と、マスコミに散々叩かれる社会的な風潮などで、行政も薬剤の承認には慎重にならざるを得ない日本では、その分、薬が世に出てくるのが遅れてしまいます。海外のdataをそのまま取り入れて承認してくれれば、我々は何とか使ってみせるという気持ちはありますが、日本全体を考えるとそうはいかないのだと思います。
|