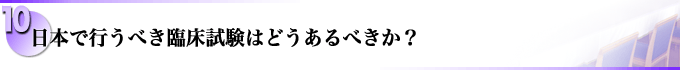 |
||
瀧内:欧米では多くの臨床試験によって、たくさんのevidenceが出てきているわけですが、日本だけが取り残されているような現状で、何らかの形で日本も大腸癌領域の臨床試験を、やっていかなければならない状況にあると思います。今後、まず日本で行うべき臨床試験とはどういうものか、各先生方にご意見をお聞きしたいのですが、何かアイディアはありませんか。 藤井:日本独自でやるのか、海外の試験の追試をするべきなのか、という問題がありますよね。FOLFOXにしても、日本人に合うかどうかということをやらなければならない。海外の試験のレビューを日本でもやってみるということは、基本的には必要ですが、日本独特の経口フッ化ピリミジン製剤がありますから、これについての臨床試験の必要があります。例えばS-1にしても新しい薬剤の併用は何らかの形でデータを出していかなければならないと思います。経口剤は在宅でできますから、普及させるにはそれが1番で、なんとか経口剤のevidenceを海外向けに発信したいですね。海外で認められるかどうかは別として、熱心にやっていくことは大事ではないですか。残念ながら欧州では、経口剤イコール、日本発のLV/UFTやS-1ではなく、capecitabineなんですから。 瀧内:荒井先生、5-FUの肝動注をCPT-11の全身投与に組み込んだアイデアはおもしろいと思うんですが、先生ご自身にとって今後是非行ってみたい臨床試験はございますか? 荒井:その前にまず全身投与の話なのですが、例えばFOLFIRIに関してですが、現状の日本に合った投与量を決める試験が必要ではないかということです。というのは、CPT-11の投与量は日本では上限がありますよね。ところが、5-FUとCPT-11の相互作用を考えると、海外のFOLFIRIをそのまま導入しても日本の上限量のCPT-11で本当に効くのかどうか甚だ疑問な訳です。日本で認可されている投与量の上限を変えるとか、投与のタイミングをずらすとかいったことを、本当に検討しないといけないと思うんです。この種の試験なら小さな規模ですぐにできますから、日本での投与法を確定する試験は行っておいた方がいいように思います。 瀧内:今のお話では、肝動注はfirst lineから撤退するという理解でよろしいんでしょうか? 荒井:肝転移だけかどうかの診断もあてにならない訳ですから、全身化学療法が力をつけてきた以上、肝動注単独をfirst lineで勝負する時代ではないと思います。むしろfirst lineの全身投与が効かなかった場合のレスキューとしての価値の方が容認されやすいでしょう。ましてや、経口薬の利便性が議論されている現状では、first lineとして固執すべき治療法ではないと思っています。手間暇かかりますしね。 瀧内:大津先生は、今年の春から吉田茂昭先生の後を引き継がれて、JCOGの消化器全体の班長として重要なポジションにおられるわけですが、今後、日本で当面やるべき臨床試験としてどういうものをお考えか、将来的に日本だけで臨床試験を行っていてもいいのかという問題にも踏み込んで、お話いただけたらと思うのですが。 大津:要するに、日本人用のdose finding studyというものをどう考えるかということですが、私自身はもう発想を変えた方がいいと思っています。日本人には海外doseは入らないと考えるのは間違いではないか、それはみんなが頭からそう思っているだけではないか。CPT-11にしてもdoseが違うのは、日本が先行し、その後海外で行なわれたphase
I studyとの差ですよね。5-FUでも、下痢の感受性が高いのは白人で、日本人の方が強いわけです。いろいろ批判は浴びるかもしれませんが、最近の国立がんセンターで行なわれている試験は、ほとんど海外用量と同等の量が推奨用量になっています。逆に、日本人が海外より低doseで使っているということが非常にまずいことをおこすのではないかという心配すらあります。 瀧内:大津先生から、インターナショナルにうって出ていくことが海外との格差を埋める最大の近道ではないかという、今までにない新しい発想の貴重なご意見をいただいたと思うのですが、朴先生も今年の春から、大津先生の後を引き継がれてJCOGの消化器内科グループの代表者になられたわけですが、JCOGの立場でも先生個人のご意見でも結構ですけれども、その点に関して何かご意見ございますか? 朴:まさしくそうだと思います。とにかく欧米に追いつくことが必要です。今後も欧米の進歩のほうが早いことは間違いありませんから、将来的には日本でも欧米と同時に始められないとまずいと思います。当面、日本で行なうべき臨床試験ということを考えた時に、例えばFOLFOX 、FOLFIRIは欧米の投与量で日本人でもできますということを証明していかないといけないと思います。まず同じ土俵に立った上で、次のグローバルの臨床試験に参加していく準備をしていきたいと思っています。 瀧内:ひとつだけ問題があるのは、CPT-11にしても承認用量がある程度限られているということですね、 大津:厚生労働省で抗がん剤併用療法検討委員会というものが組織されまして、海外の試験でphase IIIの結果が出たものは、そのまま外挿したいと考えています。その際に、日本人の安全性が問われることになりますから、それをきっちりと確保して、早く承認用量を欧米と同じに増やす方向にもっていけたらと思います。 瀧内:日本だけの時代じゃなくなってきたと。海外の臨床試験に入っていく時代だということですね。 大津: 胃癌の場合は、かなり日本と海外の差というのを言われますが、大腸癌の場合は、手術の成績とか最近のadjuvant込みの成績について、海外と日本の差はそれほど大きな差ではないですよね。 藤井:結腸癌では全く差がないと思います。ただ、直腸癌になると手術成績に差があります。直腸癌と胃癌で差があるのは、日本人の外科手術がうまいんだと言わせてもらっていいと思います。手術方法でいうと、例えばS状結腸癌では手術そのものも郭清も簡単で、そのくらいのことはアメリカと日本では差がない。ただし、直腸癌で骨盤内に入ってくるような手術とか、あるいは胃癌の郭清ということになってくると、欧米人より日本人の方が技術は上です。そこには同じ局所療法である放射線を加味すると、海外でも日本の成績と同じものを出せる。やはり土俵が違うんです。化学療法もやはり土俵が違うところがあります。CPT-11にしても、phaseⅠで欧米並みのデータがでると言いますが、施設によって違うはずです。例えばCPT-11 600mg/body など日本人にはとても考えられない。僕らは150mg/m2位と、せいぜい決められたdoseでやってます。 大津:アメリカ人研究者でも例えばweeklyでの125mg/m2がきついって言う方はいっぱいいらっしゃるんですよね。要するに、臨床試験に参加している患者さんのpopulationというのは、PSの非常に良好な方ばかりですから、そこで出てきたdoseをすべての患者に投与する必要はまったくないのです。実際、7掛け8掛けでやっていますという人も非常に多いわけです。 藤井:なんらかの方法で、患者さん個々に合ったoptimal doseを決められる方法があると思うんですよ。CPT-11ではcarboxyesteraseの活性の問題など、日本人と白人の差がもしかしたらあるかもしれない。その中で感受性試験のようなものをやって、日本人のdoseを考えていかなければならないと思います。 大津:doseの設定については、どのpopulationを対象にするかということを考えなければなりません。状態のいい患者さんのdoseを、状態のよくないpopulationに合わせたdoseと同じにしなければならないということはない。考え方を変えてもらって、そこを分けないといけないと思います。臨床試験で出てくるdoseというのは、状態のいいpopulationで決めたものですから、いずれにしても、患者さんを診ながらということになりますよね。 |
||
| 目次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | ||