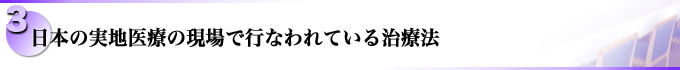 |
||
| ◆first line、second line治療の実際◆
瀧内:そうした日本の独自の状況の中で、今ある薬剤を如何に使っていくかという事が大事になってきますが、実際の現場では、何をfirst line に、何をsecond lineに使っておられるのか、お聞きしたいのですが、まず藤井先生、進行再発大腸癌における先生のfirst line、second lineを、単刀直入に教えていただけますか? 藤井:first lineは5-FU、それも今は経口のフッ化ピリミジン製剤、LV/UFTなどをfirst
lineとします。その後効果があればそのまま継続しますが、効果がなければCPT-11単剤に変更します。CPT-11単剤で効果がない場合は、併用という可能性もあります。 瀧内:先生の場合は、術前に薬剤を投与して化学療法の感受性をみておられるわけですか? 藤井:症例によってはみます。術前UFT投与の成績がよければ、はじめからUFT単剤で使いますし、効かないものには初めからCPT-11単剤を投与します。ただ何もわからない場合は、今のような使い分けを行います。 瀧内:荒井先生、先生へ紹介されてくる患者さんの多くは肝動注を希望されていると思うのですが、先生なりのfirst line、second lineにつきまして、ご意見をいただきたいと思うのですが。 荒井:実際には、他院から「肝動注を」という紹介で来られても、こちらで全身的な病巣のひろがりを診ると肝動注から入らなくてもよい患者さんが少なくありません。この場合には全身化学療法を行っています。肝動注では時間の長短は別として持続注入が基本ですので、薬剤を持続的に注入するということについては、実は僕らはかなり慣れている訳で、このため以前から5-FUの全身投与については持続静注を基本にしてやっていました。ですから、CPT-11が加わった現在は、患者さんが耐えられる状況であれば、基本的にはFOLFIRIをfirst lineにしています。年齢やその他の状況からCPT-11を使うのが躊躇される場合は5-FUの持続静注を先行し、second lineにCPT-11をもってくるという順番です。 瀧内:その場合、FOLFIRIのあとに何を持ってくるか、ということも大きな問題だと思うのですが。L-OHPが日本ではまだ使えない現状で、何を使われるのですか。 荒井:現状でFOLFIRIをfirst lineにした場合の最も切実な問題ですが、個々の症例に応じて患者さんと相談しながら決めています。思い切って無治療にすることもありますし、無治療が耐え難い場合には経口剤で一時しのぎすることもあります。ともかく「L-OHPが使えるようになるまでの期間を何とかしのぎましょう」というスタンスです。 瀧内:大津先生の施設ではどうでしょうか。 大津:first lineには、先ほどお話したようにIFLを施行します。IFLは外来でできるようになりましたが、FOLFIRIの方は5-FUが持続静注ですから外来投与が難しく、現在準備しているところです。それができるようなれば、全部FOLFIRIに代わっていくと思います。入院患者さんについてはすべてFOLFIRIに代えています。 瀧内:朴先生の施設でもやはり最初から併用療法でいかれますか? 朴:first lineはCPT-11の投与量を 100 mg/m2 としたIFLです。それがfailureした時は、以前は持続静注の5-FUに切り替え、また肝転移のみの場合は肝動注に切り替えていました。最近は、5-FU持続静注の代わりにS-1に代えてみようかなと思っています。 瀧内:今日お話を伺って驚いたのは、多くの先生方が、併用療法をfirst lineで使われているということです。 藤井:先ほども触れましたが、LV/UFTの奏効率は35%ありますので、LV/UFTでコントロールできる患者さんであれば、そのままいき、failureしたらCPT-11に切り替えるという方針でやっています。治験その他も走っていますので、始めから併用でスタートということもあります。併用すると非常によく効くんですけれども、second
lineを考えると、二つしかない大腸癌に効く薬剤の5-FUとCPT-11を使い切ってしまい、second lineがなくなります。どうしても、この二剤を使い分けしていくしかないと思います。 ◆LV/5-FUとCPT-11の、現時点での位置付けは?◆ 瀧内:大津先生のお考えでは、LV/5-FUとCPT-11の併用をfirst line治療として行うと理解してよろしいでしょうか? 大津:現時点での我々の認識では、first lineだと思いますが、ただ一般病院では、CPT-11自体、あまり使っている人が少ないので、併用がfirst lineなのかどうかは疑問ですけれど・・・。 瀧内:朴先生はいかがですか? 朴:sequentialでも、combinationでも生存期間に変わりないというdataがないですから、IFLをfirst lineに持ってこざるを得ないと思います。ただし一般病院ではCPT-11は難しいと思われているようで、あまりIFLをやっていらっしゃらないだろうと思います。当院は新設病院で、開院当初、紹介患者さんの多くは色々な薬剤の前治療が入っていましたが、CPT-11だけが使われていなかった印象があります。実際にやってみると十分外来でマネージできる治療だと感じています。 瀧内:IFLには、CPT-11を欧米のdoseで使えないという問題があると思うのですが、先生のところのdoseは、どのくらいですか。 朴:100mg/m2です。自分たちの成績をretrospectiveに評価してみたのですが、奏効率もTTPも欧米とまったく同じ結果が出ていますので、十分再現性があると思っております。開院して一年半のため、生存期間の検討は不可能ですが、TTPが7ヵ月ぐらいになりましたし、奏効率も5割前後ありました。 ◆5-FUの動注の位置付けは?◆ 瀧内:CPT-11の併用がfirst lineとして使われ始めているという状況の中で、現時点での動注療法の位置付けはどうなりますか。 荒井:ご存知のように生存期間延長についてのエビデンスを要求されると何も言えないのですが、それでも肝転移に対する腫瘍縮小効果は確実に高い訳ですし、実際、肝転移が予後を規定する状況がしばしばある訳ですから、その点から考えれば絶対にとっておきたい治療法だと言えます。それに肝動注というのは、きちんとやりさえすれば、患者さんにとって通常の全身的化学療法よりはるかに楽な治療で、この点も臨床現場での選択には重要な要素ではないかと思います。ですから、肝転移が予後を規定していることが明らかな患者さんの場合には、肝動注が第一選択になると思います。勿論「肝外病変があれば全身化学療法」という意見もありますが、「画像診断による肝外病変の有無」というのはかなりあてにならなくて、初めに画像診断で肝転移のみと診断していても、後でごろごろ他病変が見つかる症例はたくさんあります。実際にはこういった症例でも、まず肝転移を何とかしなければ予後は全く期待できない訳ですから、肝転移が主たる病巣であって、それが予後規定因子である患者さんについては、肝動注を治療の軸に置くことは十分に許容されるのではないかと思います。 |
||
| 目次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | ||