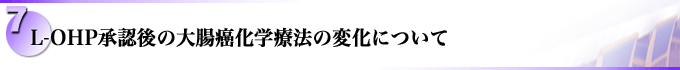 |
||
瀧内:現状経口剤は慎重に対応すべきだとすれば、日本の大腸癌化学療法が大きく変化するのは、やはりL-OHPが承認されてからということになりますか? 大津:進行再発の場合とAdjuvantの場合ではまたちょっと違いますが、進行・再発の場合であれば、L-OHPが入ってくるとやはり、随分変わってくると思います。 瀧内:L-OHPあるいはCPT-11のどちらをfirst lineに使うのかという問題があるものの、現状としては大きく変わってくることは間違いなく、そして新たなsecond
line のオプションも出てくるということですね。 藤井:既に並行輸入で何例かL-OHPを使っていますが、かなり副作用が強いので、日本人に合うか合わないかというのは、何例か投与してみないとわからないのではないかと思っています。今までとちょっと違う副作用ですから。日本人は今まで消化器毒性や血液毒性には慣れていますけれども、いわゆるクラッシュアイスシンドロームといわれる、今まで経験したことのない副作用がありますので、奏効率がよくてもなかなか使いにくいという問題が出てくるのではないかと思います。 瀧内:結局、重要なkey drugとしてL-OHPとCPT-11、LV/5-FUの三剤があげられ、これら三剤をいかに使っていくのかが、今後日本において問われてくると思いますが、標準治療としての三剤の使い方について、朴先生、ご意見をお聞かせください。 朴:FOLFOXがIFLに勝ったと言うN9741試験の結果がありましたし、FOLFOXとFOLFIRIのクロスオーバー試験では両者に違いはなかったという結果でした。どちらを先に使用するのがよいかという話になりますと、FOLFOXを先にもって来ると、条件の悪いsecond lineでCPT-11が使いにくくなる可能性があります。逆にFOLFIRIを先に使用すると毒性が少ない点で有利であると思います。ただしcetuximab(IMC-C225)などの新薬が入ってきた場合、これらはCPT-11との相性がよいですから、second lineでCPT-11とcetuximabを併用したほうがよいかもしれないというような難しい問題が出てくると思います。世界的にFOLFOXがメインになりつつありますので、L-OHPが承認されて使えるようになったら、やはりFOLFOXを先に持ってきて、second lineでCPT-11を使うだろうと思います。 瀧内:その場合、CPT-11は単独になりますか、あるいは何らかの併用ですか? 朴:併用になると思います。そこでcetuximabが使えれば大変うれしいですけれど。 瀧内:その場合に、first lineに使用するFOLFOXですが、5-FUのbolus投与が加わった5-FU持続静注のregimenになりますが、LV+bolus 5-FU+L-OHPというregimenは使われますか? 朴:weeklyのbolus投与のLV/5-FU(Roswell Pank regimen)にL-OHPを併用する投与法がありますが、効果や毒性の点でFOLFOXと比較してどうなのか、まだ本当のところはわかりません。 瀧内:大津先生はどう判断されますか? 先生はやはりL-OHPをfirst lineへ持っていかれますか? 大津:N9741試験の成績はありますが、先ほど触れたクロスオーバー試験の結果は両者に違いがないので、FOLFIRIでもFOLFOXでもかまわないと思います。欧米の研究者の話を聞いてもCPT-11の方が副作用が強いと言う人もいるし、L-OHPの方が使いにくいと言う人もいて、好みが分かれますね。副作用のprofileが違うので意見が分かれるところです。日本では一般的にはCPT-11を嫌う方が多いようですから、L-OHPをfirst
line に持ってくることが多くなるのではないかと思います。 |
||
|
||
| 目次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | ||
