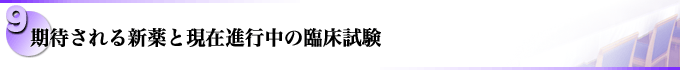 |
||
瀧内:今後多くの薬剤が登場し、生存が延長してくると、second line以降をどうするかという治療戦略も非常に大事になってくると思います。先ほど朴先生からも出たcetuximabなど、分子標的薬剤もどんどん開発されていますが、近い将来期待されるであろう分子標的薬剤について、大津先生から情報提供をしていただきたいと思います。 大津:ご承知のとおり、FDAがbevacizumabとcetuximabを承認しました。作用のターゲットはVEGF receptorとEGF receptorの二つが中心で、さまざまな類似薬剤が多数開発されてきていますし、日本でもすでにいくつかphase Iに入っています。日本で大腸癌を対象とした開発品の中でもっとも早いのは、bevacizumabとcetuximabで、cetuximabはすでに開始されていますが、bevacizumabはこれからphase Iです。その他、tyrosin kinase阻害剤、malti-targetの阻害剤など、signal transductionの阻害剤などもいくつも開発中です。分子標的薬剤に関しては、かなり目白押しですね。 瀧内:欧米のデータを見ると、CPT-11が分子標的薬剤と組み合わせた場合に、かなり成績がいいようですね。 大津:アメリカでL-OHPが承認されてから日が浅いですから、そのせいでCPT-11のデータが多いのか、本当にCPT-11がいいのかわかりません。今年から来年にかけて、L-OHPとの併用成績もいくつか発表されてくるようですから、注目したいですね。 瀧内:その意味でも、さまざまな臨床試験が動いていると思うのですが、海外も含めて、朴先生が注目されておられる臨床試験をご紹介いただけますか? 朴:FOLFOXに対しては、±cetuximab、±bevacizumabを注目しています。また、経口剤が取って代われるかどうかということでは、FOLFOX
vs XELOX(capecitabine + L-OHP)にも注目したいですね。 |
||
|
||
| 目次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | ||
