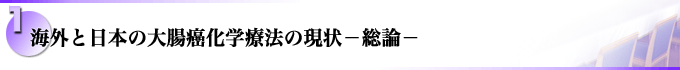 |
||
瀧内:本日は大変お忙しい中、近年進歩目覚しい大腸癌化学療法の現状と将来〜今後の治療戦略を考える〜という座談会に、各科からご専門の先生方にお集まりいただきました。本日の座談会では各先生方に、それぞれのお立場から大腸癌化学療法に対する最新のお考えをお聞きし、今後の方向性についてsuggestionをいただければと思います。 朴: 従来のLV/5-FUについては、米国でbolus投与が、欧州では持続静注投与の開発が、それぞれ進んできました。ところが、CPT-11やoxaliplatin(L-OHP)が加わり、それらとの併用効果をみたN9741試験とGERCOR試験の結果が出たため、LV/5-FUにCPT-11やL-OHPを付加したFOLFOX、FOLFIRIがfirst
lineでも標準治療と位置づけられるようになりました。 瀧内:しかし、日本ではL-OHPがまだ承認されていないという大きな問題があり、海外と日本の状況には大きな差異がありますが、大津先生、日本の現状はいかがでしょうか。 大津:L-OHPが未承認なので、日本で使用可能なのはCPT-11、Isovorin®(l-LV)/5-FUの二つというのが現状です。内科では施設間に差があるものの、基本的には初回治療はLV/5-FU+CPT-11の併用になります。これまではSaltz
regimen(LV/5-FU+CPT-11:IFL)が中心だったかと思いますが、いくつかの比較試験の成績で、5-FUの投与法がbolusより持続静注の方が安全性で優れているということがわかり、FOLFIRI中心に変わりつつあると思います。 瀧内:藤井先生、外科の先生の立場からのご意見で結構ですが、実地でどういう治療をされていますか。 藤井:外科ではまずadjuvant療法に、あいかわらず経口フッ化ピリミジン製剤を、stage IIIや、少し進んだstage IIに使用し、進行癌については、5-FU系薬剤にl-LVを併用し、場合によってCPT-11を併用するということになります。 瀧内:外科の先生方も、進行再発癌症例に対しては最初から多剤併用療法を積極的にされるようになってきたということですね。 藤井:CPT-11に関しては、初期に比べればかなり積極的に使うようになってきました。 瀧内:荒井先生は動注療法で大変よい成績を上げられていますが、このようなCPT-11に代表される新薬による化学療法の変化を踏まえて、動注療法の現状をどうお考えですか。 |
||
|
||
| 目次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | ||
