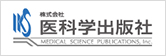吉野:ありがとうございました。先生方は原発部位が治療戦略に影響を及ぼすと思いますか。影響するとしたら、左側と右側でそれぞれどのような治療戦略を考えますか。
山口:原発部位は治療選択に影響すると思います。原発巣が左側の場合はFOLFOXあるいはFOLFIRIに抗EGFR抗体薬を併用します。一方、右側の場合はRAS野生型であってもFOLFOXIRI+Bevacizumabを選択するようにしています。
谷口:私も原発部位は治療選択に影響を及ぼすと思います。左側の症例には、これまで以上に抗EGFR抗体薬を積極的に選択するようになりました。右側の場合には今までと比べて抗EGFR抗体薬の使用に消極的になり、腫瘍縮小をねらうときはFOLFOXIRI+Bevacizumabを選択することが多くなりました。右側の場合で腫瘍縮小をねらわないときはFOLFOX+Bevacizumabが多いです。
結城:当施設では右側の場合はBevacizumabを併用します。左側の場合はケースバイケースで、患者さんの状態をみながら、Bevacizumabと抗EGFR抗体薬の有害事象に関する説明を行った上で、Bevacizumabを選択することもあります。
植竹:腫瘍径がある程度の大きさ以上で、かつ原発巣が左側であれば、積極的に抗EGFR抗体薬を使用しています。一方、左側の原発巣を切除した後に肝臓に陰影が現れ、経過観察中に増大して肝転移が確定したような異時性の小さな肝再発のときは、もとの原発巣部位は左側ですが、1st-lineはFOLFOX+Bevacizumabで治療を開始します。
吉野:NCCNガイドラインは「原発巣が左側のRAS野生型に抗EGFR抗体薬を選択肢の1つとして提示している、ただし右側には使用しないことを推奨している」と理解しています。それでは「原発部位に基づいて治療方針を決定し、NCCNガイドラインにあるその他のレジメンは選択肢から外してもよいか?」と聞かれたら、先生方はどのように答えますか。
山口:さまざまなファクターが絡みますから、原発部位だけでその他のレジメンを選択肢から外すべきではないと思います。しかし、わたし自身は、2年生存率、3年生存率がより良好な戦略を考えると、原発巣が左側部位の腫瘍には1st-lineに抗EGFR抗体薬を極力使うべきであるという考えは変わりません。
吉野:良好な生存率が期待できるレジメンを選ぶべきということですね。
山口:そうです。
結城:現在、原発部位に関する2つの第III相試験が進行中ですから、それらの結果が出れば、明確な答えがみえてくると思います。

植竹:私はDepth of Response(DpR)も重視しています。切除可能な大腸癌肝転移症例を対象として、周術期の化学療法±Cetuximabを比較したnew EPOC試験では、奏効率はCetuximab併用群の方が良好であったにもかかわらず、PFSではCetuximab併用群にdetrimental effectがみられました。このことから、もし異時性の癌で、かつ腫瘍量が小さい場合は、左側部位でも抗EGFR抗体薬を使用してよいかは疑問です。
吉野:異時性、腫瘍量などのファクターも考慮すると、原発部位だけでは決まらないこともあるというご意見ですね。
山口:将来的に予後や治療効果に関連する分子マーカーが十分に明らかになれば、もっと明確なclassificationが見出だせるかもしれませんが、それは今後の課題でしょう。
吉野:原発部位による腫瘍の特性の違いを裏打ちするbiologyが包括的に解明される時代になれば、tumor locationをsurrogateマーカーとする必要はありませんね。現時点において、1st-lineでどのような治療戦略を立てるかは主治医がこれまでのデータをどのように判断・活用するかにかかってくると思います。