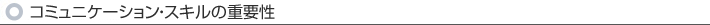
 佐藤
佐藤 固形癌の治療では、手術をはじめとする集学的治療が行われますが、治癒が非常に難しい状態の患者さんが多いのも現状です。
そのため、大半の場合、がん治療に関わる医師は「がんである」こと、特に腫瘍内科医は「治癒の難しいがんである」という非常に“悪い知らせ”を告知することから診療を始めることになります。また、抗がん治療を続けてもメリットはないと考えられる場合には、「積極的治療の中止」を伝える必要があります。これも患者さんやご家族にとっては非常に“悪い知らせ”であり、きわめて大きな衝撃となります。
このように、抗がん治療には“悪い知らせ”を伝える場面が多く、医師には相応のコミュニケーション・スキルが求められます
(表1)。日本サイコオンコロジー学会では、がん治療におけるコミュニケーション・スキルを訓練するための研修会 (Communication Skill Training : CST) を実施していますので、まずは明智先生に概要を説明していただきたいと思います。
明智 積極的治療ができなくなった進行癌の患者さんは、非常に精神的負担や心理的苦痛が強い状態と考えられますが、医師とのコミュニケーションにより納得して治療を受けることで、患者さんやそのご家族の心理的苦痛が軽減され、医療への満足感が高まることが知られています。実際に「医師とのコミュニケーションが患者さんの抗がん治療に対するアドヒアランスに影響する」とのエビデンスもあります。また、医療者にとっても、「burnoutの予防になる」「専門職としての充実感が増す」「訴訟のリスクが減少する」といったメリットがあるといわれています
1-3)。
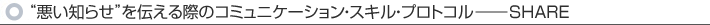
明智 がん治療における“悪い知らせ”を伝える場合のコミュニケーション・スキルとしては、10年ほど前に米国で作成された「SPIKES」というプロトコルがあるのですが、「文化の異なる日本人にそのまま応用してもよいのだろうか」という問題点も指摘されていました。そこで、国立がん研究センターの内富庸介先生 (現・岡山大学大学院)、藤森麻衣子先生らが中心となり、がん患者さん529例を対象に「“悪い知らせ”を伝える際にどのように伝えてほしいか」をインタビューし、その結果を (1) 場の設定、(2) 伝える内容、(3) 伝え方、(4) 情緒的サポートの4つのコンポーネントに分けてまとめました
4) (表2)。
欧米と共通した一般的な内容も多いのですが、日本人ならではの項目もいくつかあります。その1つが「家族にも一緒に伝えてほしい」というもので、これは日本人に特徴的だといわれています。予後については議論のあるところですが、予後に関する情報を知りたい方は約半数で、欧米に比べるとやや少なめです。
そして、がん治療医の先生方には大変だと思うのですが、「情緒的サポートも同時に提供してほしい」というのが、患者さん側からあがってきた希望です。“悪い知らせ”に対し動揺し、精神的につらい状態になったときに、共感的・支持的に対応してほしい。さらに、「家族にも配慮してほしい」というのは、日本人に特徴的な要素ですね。
これらの研究結果をもとに作成されたのが、日本のがん治療における“悪い知らせ”を伝えるためのコミュニケーション・スキルのプロトコルである「
SHARE」です。日本サイコオンコロジー学会では厚生労働省の委託事業として、がん治療に携わる医師を対象に、SHAREに基づいたコミュニケーション・スキルの研修会を定期的に開催しています (参照:
日本サイコオンコロジー学会 コミュニケーション技術研修会)。

SHAREでは具体的な項目が挙げられています。例えば、「環境の設定」に関しては、プライバシーの保たれた落ち着いた場所であること。「悪い知らせの伝え方」については、悪い知らせを伝える前に現在の状況に対する患者さんの認識を確認すること。また、「付加的情報の提供」としては、患者さんが望む話題、特に社会的な情報――今後の日常生活や仕事について話し合うことなどが挙げられています。
最も難しいと思われる「安心感と情緒的サポートの提供」の内容で興味深いのは、患者さんは「悪い知らせの伝え方」では、病名も含めて正直に詳しく伝えてほしいと望んでいる一方で、“がん”という言葉を何度も繰り返してほしくないと考えている点です。また、「痛みはきっととれますよ」というちょっとした言葉が、実は患者さんが望んでいる、希望をもてる情報であることも示唆されています。
佐藤 私もSHAREの研修会を受けた1人で、実際のインフォームド・コンセント
(IC) などでも、SHAREの内容を意識しながら話をしています。SHAREの内容は、
日本サイコオンコロジー学会のwebサイトで閲覧できます。このGI cancer-netのサイトでも、以前SHAREと“悪い知らせ”を伝える際のロールプレイを取り上げたコンテンツがありますので、参考にしていただけたらと思います (参照:「
BAD NEWSのGOODな伝え方」)。

 SHAREでは具体的な項目が挙げられています。例えば、「環境の設定」に関しては、プライバシーの保たれた落ち着いた場所であること。「悪い知らせの伝え方」については、悪い知らせを伝える前に現在の状況に対する患者さんの認識を確認すること。また、「付加的情報の提供」としては、患者さんが望む話題、特に社会的な情報――今後の日常生活や仕事について話し合うことなどが挙げられています。
SHAREでは具体的な項目が挙げられています。例えば、「環境の設定」に関しては、プライバシーの保たれた落ち着いた場所であること。「悪い知らせの伝え方」については、悪い知らせを伝える前に現在の状況に対する患者さんの認識を確認すること。また、「付加的情報の提供」としては、患者さんが望む話題、特に社会的な情報――今後の日常生活や仕事について話し合うことなどが挙げられています。


