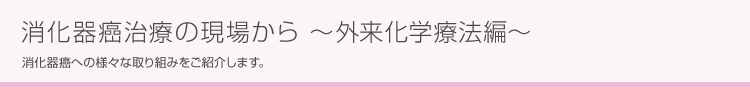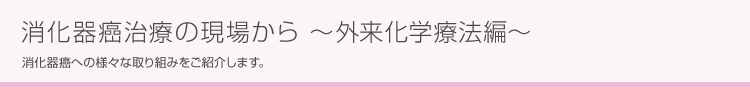Q. 副作用対策や、患者さんへの情報提供はどのようにされていますか。
|
A: 看護師から個別に説明して対応しています。患者さん用のパンフレットを作成し、それを活用しています。パンフレットは、化学療法全般について書かれた共通のものを基本に、看護師から追加説明する形をとっていますが、特殊なプロトコール(FOLFOXなど)については、その特徴を書いた資料を個別に作成して説明しています。 |
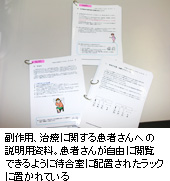 |
Q. 治療中や治療後に帰宅してからの緊急時の対応はどうなっていますか。
A: 「緊急時対策マニュアル」を策定しており、それに則って行動します。救急カートにひと通りのものは準備していますが、実際に何か起こったら救急部に搬送することになると思います。帰宅後の患者さんからの連絡は救急部から各診療科にまわり、各科で対応することになります。当センターには診療スペースはありませんので、治療の判断は各診療科外来で主治医が行うのが基本です。ですから、薬剤投与中に患者さんが治療に耐えられそうにないと思われたときも、当センターの医師または看護師から主治医へと連絡し、判断を仰ぐことになります。
Q. この外来化学療法部門の業務について、院内への広報は行っていますか。
A: われわれが作成しているわけではありませんが、当院の「医師業務マニュアル」に記載されています。
Q. 院内の医師やコメディカルへの教育はどのように実施されていますか。
A: 当センターの専任スタッフが中心となり、専任医師による他診療科の医師や看護師に対する教育、専門看護師から他の一般看護師への教育、または勉強会などを行っています。薬剤師も参加しています。
Q. 今後、同様の施設を開設される他院の方々に、先駆者からのアドバイスをお願いします。
A: まずは始めてみることです。机上で考えて、理想を求めても何も始まりません。われわれも、既存の施設を利用するところから始めました。使い勝手の悪さもありますが、実際に業務を経験することにより、必要なものとそうでないものがみえてきます。その経験をもとに、われわれも移転後はより機能的な施設とシステムをつくりあげることができると思っています。そして、しっかりとした目的をもって、医師はもちろん、看護師をはじめとしたコメディカルが積極的に参加することも重要です。実際に患者さんと接する時間の長いコメディカルが、知識、技術、そしてモチベーションをもって積極的に関わることなしに外来化学療法の成功はあり得ないと考えています。
インタビュアーからのコメント 佐藤 温先生
近年、外来化学療法は医療側および患者側のニーズに応えて、広く認識され、急速に普及しつつあります。しかしそのシステムについては、まだまだ各施設がよりよい形態を求めて試行錯誤している段階です。今回の取材において、大学病院におけるそのシステムを勉強できたことは大変有意義でした。私は、日頃より癌治療は内科、外科という縦割りの区別ではなく、癌治療全体をセンター化して横断的に診ていくことが必要になると考えていますが、外来化学療法は、そのための第一歩になりうると思います。診療科の縦の壁を取り払い、横の連携をつくるための突破口となることを期待しています。
また、今回の訪問で看護師から聞いたお話は、現実を再認識させられました。看護師の認定制度について、医師はあまり知識をもっていないのが実状だと思います。医師の専門医制度と同じで、こうした資格は、医療従事者のモチベーションを高めることにつながります。専門的知識をもった看護師に積極的に参加してもらうために、認定制度の活用をバックアップし、それに応じた活躍の場を用意することが大切です。お互いに協力して任務を遂行するために、医師もそうしたことにも目を向けるべきなのでしょう。