|
|
|
瀧内:では、日本における現時点での結腸癌術後補助化学療法の標準的治療はどうでしょう。 三嶋:最も汎用されているものを標準と考えるのか、現時点で最も有効と考えられるものを標準と考えるのかによっても違ってきます。汎用されているものと考えるなら、日本では外科医が補助化学療法を行っている施設が大半なので、経口抗癌剤を使っているケースが多いと思います。一方、最も有効なものを標準と考えるなら、『大腸癌治療ガイドライン』に記載されているLV/5-FU(注射)もしくはLV/UFT(経口)が標準と考えられます(表)。 瀧内:ということは、RPMI regimenあるいはそれに準じた成績が得られたことで、実臨床ではLV/UFT療法も標準的治療の位置づけだと考えてよいわけですね。 |
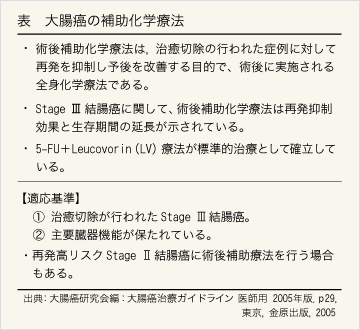 |
貞廣:三嶋先生に同感です。2年前のNSABP C-06の発表以降は、経静脈的なRPMI regimenを中心にしたLV/5-FUおよび経口のLV/UFTが、日本での標準的治療としての位置を確立していると考えます。
瀧内:貞廣先生は肝転移を抑制する目的で、肝動注を組み込んだトライアルを行われていますね。
貞廣:無作為化試験を行って、5-FUを経肝動脈で投与することによって死亡が60%近く低減されることを発表したのですが、これには追試が必要です。ただ、これまでの全身化学療法に比べて、結腸癌で最も多い再発形式である肝転移を選択的に抑えるというアプローチも成立するのではないかと提言をさせていただいています。
瀧内:坂本先生も経口抗癌剤のメタアナリシスを行っていらっしゃいますが、先生自身は日本における標準的治療をどうお考えでしょうか。
坂本:日本のクリニカルプラクティスではUFTやTS-1の単剤治療が行われていますが、現時点では経口剤のなかで本当にエビデンスがあるのはLV/UFT療法です。
 瀧内:海外ではLV/5-FUをベースにいろんな薬剤を加えて検討する戦略をとってきていますね。L-OHPの追加では非常によい成績が得られたので、次のステップとしては当然、転移性大腸癌で良好なデータが出ている分子標的薬を術後補助化学療法にも加えていく戦略が見え隠れするわけですが。
瀧内:海外ではLV/5-FUをベースにいろんな薬剤を加えて検討する戦略をとってきていますね。L-OHPの追加では非常によい成績が得られたので、次のステップとしては当然、転移性大腸癌で良好なデータが出ている分子標的薬を術後補助化学療法にも加えていく戦略が見え隠れするわけですが。
大津:現在進行中のAVANT試験では、FOLFOX 4±bevacizumabとXELOX+bevacizmabの試験が進行中で、われわれも含め日本からも5施設程度、参加予定です。
瀧内:海外のregimenは少し煩雑な面もあるのですが、MOSAIC試験の結果を受けて、今後は日本でもFOLFOX等の評価をしていく必要があるとお考えですか。
三嶋:FOLFOXを転移癌に行うのはよいのですが、術後補助化学療法にまで適用するには今の一般病院のマンパワーでは不十分だと心配します。また、強力な化学療法を行う場合、その副作用に一般外科医が十分対応できるかという問題もあります。日本には化学療法の専門医が少なく、外科医が手術も化学療法も行っている現状のなかで、どのように対応していくかが重要です。実際には外科であれ内科であれ、きちんとした化学療法ができる医師が行えば問題ないと思いますが。
|
瀧内:Oncologistが増えてくればよいということですね。 貞廣:MOSAIC、それからNSABP C-07におけるL-OHPの上乗せ効果は率直に認めるべきですが、MOSAICではグレード3以上の好中球減少が41%、NSABP C-07ではグレード3以上の下痢が38%もみられています。これはかなりの高率です。私自身の経験ではそれほど重篤な印象はないのですが、実際の臨床においてはL-OHPの5%の上乗せ効果と重篤な副作用の発現、それから補助化学療法に対する患者さんの考え方も考慮して、何がベストか考えるべきだと思います。 瀧内:内科医の立場からみると、それらの毒性が本当に重篤かどうかは議論のあるところだと思います。日常臨床においてFOLFOXは比較的行いやすい治療だという印象があり、外来で十分に管理できると私自身は思っているのですが。 |
 |
坂本:外科医も最善の治療を患者さんに行いたいという気持ちは同じですが、外科の日常診療が多岐にわたっている現状からみるとそれが難しいことも事実なので、そのことを患者さんにきちんとインフォームし、患者さんが希望する場合は臨床腫瘍医がいる施設を紹介するなどして、できるだけ最善の治療を提供できる可能性を模索していく必要があると思います。
  |
