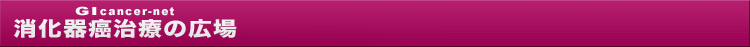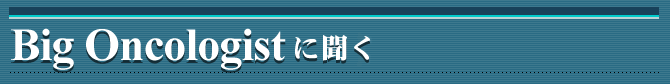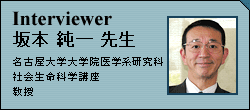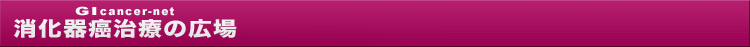|
直腸癌における放射線治療は有効か |
|
 |
|
| 直腸癌について伺います。日本では経口フッ化ピリミジンがキードラッグとなっています。欧米ではほとんどのケースで術前照射を採用していますが、この方法では適切な外科手術を行う上で、さまざまな問題が生じると考えられます。日本と欧米諸国のアプローチの違いをうまく融合させることはできませんか。 |
| 日本では放射線治療を行わないということですか。術後でもそうなのでしょうか。 |
| その通りです。きわめて進行した症例では術中照射を行うことがありますが、欧米の考え方とはまったく異なります。実際、放射線療法に関するエビデンスはスウェーデンの直腸癌試験の結果(N Engl J Med. 1997;336: 980)のみであり、それ以外の試験は明確なエビデンスを出していませんね。 |
放射線治療は複雑な問題です。直腸癌における放射線治療試験のメタアナリシスでは、放射線治療にわずかな効果しか認められませんでした(Lancet. 2001;358:1291)。確かに局所再発には効果がありましたが、OSへの作用はかなり不明確だったのです。高齢者には特に、放射線治療の毒性がベネフィットを上回っていました。若年患者であればいくらかベネフィットがあるようですが、高齢者への照射はあまり適切ではないでしょう。
放射線治療の適用については不明な点がいくつもあるのが事実です。現在欧州では、術前照射だけでなく化学療法を加える傾向にあり、最善のレジメを摸索しているところです。フランスではLV/5-FU とCPT-11を用いた大規模な試験がスタートしますし、術前にoxaliplatinを投与する試験などもあります。進行中の試験が複数ありますが、結果はまだ明らかになっていないのが現状です。
|
 |
術前照射および外科手術に対する日本と欧米の差異 |
|
 |
|
| 欧米では直腸癌も結腸癌と同じく、LV/5-FUプラス放射線治療が主な治療法と考えてよいでしょうか。 |
| 欧州ではそうなっており、米国でも同様です。ただし米国では、現在は術前照射にシフトしたものの、過去長い間、術後照射を好んで採用していました。私の見解では、放射線治療のエビデンスはまだ不十分なように思います。すべての患者に適用できるレベル1のエビデンスを有する治療であるとは思っていません。 |
| これは日本の腫瘍専門医にとって、とても励みになる言葉です。我々はほとんどの患者に対して、術前も術後も照射は行っていませんので。 |
| エビデンスはないものの、多くの人が、外科手術が適切であれば放射線治療は必要ないと考えています。 |
| 我々はいつもそのように主張しています。 |
確かに日本の理論の成果は欧州や米国よりもはるかに優れているようにみえます。しかし疾患の自然史も違いますし、人種差もあるでしょうから、比較は難しいのです。
治療結果が主に外科医の腕に左右されるのか、患者の特性に左右されるのかについて、明確な答えはないように思います。ご存知のように、オランダでは以前胃癌を対象として広域および狭域のリンパ節郭清術を比較する無作為試験(J Clin Oncol. 2004; 22: 2069)を行い、引き続き直腸癌でも外科手術の比較を行っています。結果はまだ公表されていないと思いますが、私が聞いたところでは、より徹底的な外科手術と、そうでない手術の成績に大きな有意差はないようです。これは患者の問題かもしれません。欧米の患者の場合、より徹底的な外科手術が何らかの理由から有効ではない可能性があります。患者を「日本人」と「欧州人」に割り付けることはできないため、こうした問題を検証するのはとても困難です。 |
| いずれにしても、現時点での欧米諸国の標準治療はLV/5-FUと術前の放射線治療であり、先生方はこれにCPT-11などを加えようとしていらっしゃるのですね。 |
| そうです。今、この方法を術前化学療法として実施しようとしており、これから実証していくところです。私が知る限り、これがよりよい治療法であるというエビデンスはまだ得られていません。 |
 |
臨床試験推進に関するフランスの試み |
|
 |
|
| 先生は数々の臨床試験について、世界各国で専門的助言をし、また指揮・指導をしていらっしゃいます。フランスにおける最近の活動についてお聞かせください。 |
現在、フランスのオンコロジー領域では、政府が国立癌研究所を創設したことが大きなニュースとなっています。この研究所には数多くの使命がありますが、最大の使命は国民誰もが癌治療を等しく受けられるようにすることです。フランスの有名な理念である「自由・平等・博愛」に立ち返るというわけです。
別の動機として、フランスでは臨床試験に参加する患者がわずか4%と、ごく少数であることも挙げられます。 |
| 日本はもっと低い数字です。 |
4%というのは低すぎます。英国でも「National Cancer Research Network」が2001年に創設され、試験参加率が4%から10%以上に増加しています。3年後、またお話しする機会があれば、おそらくフランスの患者の10%が臨床試験に参加していると申し上げられるでしょう。それが正しかろうが間違っていようが、臨床試験が治療法を改善していく唯一の方法だと、皆信じているためです。
このため、より多くの臨床試験を行い、より多くの患者に参加いただく必要があります。我々が目指しているのは、さまざまな対策、地域レベルのネットワークを立ち上げて臨床試験を改善することであり、重要な問題に関する大規模な臨床試験を国家レベルで推進していくことです。
我々は、たとえば新薬の恩恵を受けるであろう患者には、確実にそれが投与できるようにしなければなりません。そのための経費を妥当なものにするためにも、さらに臨床研究を進めていく必要があります。 |
そうですね。資源は限られているのですから、responderとnon-responderをまず分ける必要があり、また、それを実証せねばならないでしょう。
新しいプロジェクトにおける先生の任務はどのようなものですか。生物統計学と臨床試験のディレクターだと伺っていますが。 |
私の任務はフランス国内の臨床試験の数を増やし、かつ優れた試験を実施することです。現時点では、あらゆる癌の病理を適切な臨床試験で研究していく体制を整えようとしています。
フランス国内で実施できる場合は国内のみで進めますが、さらに多くの被験者が必要であれば、欧州諸国と手を組むか、ときには世界規模の共同研究が可能です。
EORTCともさまざまな共同事業を進めたいと思っています。EORTC試験へのフランス側の参加は現在低いレベルであり、この点も変わっていく必要があります。さまざまな点を改善していく必要があり、そのためには種々の方法があると考えています。 |
| 今後はベルギーとフランスを行き来することになるのですね。とても興味深く、また有益なお話しをありがとうございました。 |
 |