 |
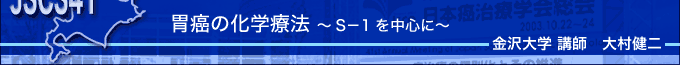 |
| |前の頁に戻る| |
| S-1とCDDPの併用化学療法 〜進行・再発胃癌〜 三田地泰司ら(仙台厚生病院消化器センター消化器内科)は、高度進行・切除不能胃癌例に対するS-1/CDDP併用療法を検討した(OS112-1)。 高度進行・切除不能胃癌を対象として行なったS-1/CDDP併用療法においてCDDPの投与量を低用量(2-6 mg/m2 day1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 4週投与2週休薬)とCDDP高用量(60-80 mg/m2 day8, 3週投与2週休薬)に分けて比較検討を行なった。 その結果、低用量(6例)ではPR 4例(RR 66.7%)、MST 678日、高用量(9例)ではPR 5例(RR 55.6%)、MST 228日だった。低用量投与の症例では原発巣、転移巣いずれにおいても、高用量投与例に劣らない抗腫瘍効果を認めた。なお、有害事象はいずれの場合も対応可能なものだった。 外来化学療法としては、低用量連日投与は施行が困難である。今後さらに、新たな投与量とスケジュールを探る必要があるとの見解が示された。 平川弘聖ら(大阪市立大学腫瘍外科)は、S-1+低用量CDDP連日投与法のphase Iの成績を発表した(OS112-3)。 進行再発胃癌患者を対象としたphase I studyであり、S-1の投与量は40 mg/m2 1日2回 連日投与(4週投与2週休薬)に固定した。一方、CDDPについては1, 2, 3, 4, 6 mg/m2の5段階のlevelを設け、5投2休とし(4週投与2週休薬)、2サイクル以上投与できた例についてlevelごとに有害事象の発現とその程度を評価した。 その結果、CDDP 6 mg/m2投与例では3日以上のgrade 4の白血球減少、好中球減少およびgrade 4の血小板減少が出現した。4 mg/m2投与ではdose limiting toxicity(DLT)は出現せず、本療法におけるCDDPの推奨用量 は4 mg/m2であると報告された。なお、5-FUの血中濃度はCDDPの投与量に関わらずほぼ同等であったが、CDDPの血中濃度は投与量の増加と共に有意に上昇した。 フロアからは、このregimenではQOLが低下するのではないかとの指摘があった。それに対し、本regimenでは最低3ヵ月の入院が必要であり、既に外来治療可能なregimenの検討に着手しているとの回答があった。 近藤建ら(国立名古屋病院外科)は、経口剤S-1の利点を生かし、QOLを良好に保つことを目的としたS-1/低用量CDDPのweekly投与法のphase I studyを報告した(OS112-4)。 進行再発胃癌12例に対し、S-1の80 mg/m2 分2 3週投与2週休薬に、CDDPは20 mg/m2, 25 mg/m2, 30 mg/m2の3 levelを設けてday 8, 15, 22にそれぞれ投与し、2サイクル以上実施して検討を加えた。 その結果、CDDP 30mg/m2投与ではgrade 4の好中球減少が1例、grade 3の悪心・嘔吐が1例に認められ、DLTと判断された。なお参考値ながらRRは62.5%(5/8)、50%生存は383日であった。20 mg/m2投与例にはPRは認められなかった。この結果を受け、CDDP 25 mg/m2投与を推奨用量とし、phase IIを開始していることが付け加えられた。 質疑の中で、S-1では消化管上皮内のFdUMP産生が抑えられているので、CDDPをdose upするにつれて頻度と程度が高まる消化管毒性は、CDDPの固有の細胞毒性によるものと解釈すべきであるとの意見が出された。また、低量反復投与も含めて、CDDPをS-1に併用することでS-1の骨髄毒性が格段に増強される現象が認められないのは、CDDPに細胞内の還元型葉酸濃度を増加させる作用がないことの証拠ではないかとの指摘があった。現在、S-1と還元型葉酸製剤の併用は禁忌である。臨床の場で誤った薬剤併用がなされないためにも、biochemical modulationに関する理論のうち、改めるべき点は訂正する必要があると思われる。 さらに、1990年代後半に盛んに用いられた低用量CDDP/5-FUでは、各薬剤の用法や用量が施設によってまちまちであったため、何のevidenceも得られていないばかりでなく、最適な投与法すら判明していないとの発言があった。さらにS-1/CDDPでは同じ轍を踏むことなく、個性的regimenの開発は控えてrandomized clinical trial(RCT)を行ない、evidenceを世に示すべきであると付け加えられた。きわめて重要な指摘であったと考えられる。 S-1と併用する際のCDDPの投与法は 1)高用量を1サイクル1回(day 8) 2)中等量を週に1回3週連続(day 8, 15, 22) 3)低用量を5投2休で4週連続 の3つに絞られた。各々についてphase I studyが施行されたことになり、今後の発展が期待される。いずれの投与法も外来での施行を視野に入れたものであるが、外来通院の頻度の多寡やhydrationが必要か否かなど長所と短所を合わせ持つ。主治医は、患者の都合などを勘案してこれらを使い分けることになろう。なお、CDDP/5-FUにみられたようなregimenの混乱を回避するためにも、これら3種の投与法と比較して格段に優れているという理論的根拠がない限り、新たなCDDP投与法の開発は慎むべきであると考えられる。 S-1とTaxaneの併用化学療法 〜進行・再発胃癌〜 里見絵里子ら(国立病院大阪医療センター消化器科)は、進行再発胃癌を対象として進行中であるS-1/TXLのphase I/II の成績を報告した(OS116-1)。 進行再発胃癌16症例を対象とした。S-1は80 mg/m2 分2をday 1〜14に投与、TXLは50ないし60 mg/m2/dayをday 1, 8にdivし、3週間を1サイクルとして繰り返した。6サイクルまでに13例がPDやPSの低下などで投与中止となった。 有害事象としては、grade 3の好中球減少、食欲不振などがみられた。評価可能な11例で、PRは6例、SDは3例、PDは2例、RRは55%であった。 投与中止となった13例にはsecond line化学療法が施行され、またthird lineに進んだ症例もあった。S-1/TXLにおけるTXLの推奨用量は50 mg/m2であった。S-1/TXLは安全に施行可能で有用なregimenと結論付けられた。 梶本仙子ら(大阪府成人病センター消化器内科)は、手術不能進行胃癌16例を対象とし、S-1/TXLの安全性と有効性を検討した(OS116-2)。 S-1は80 mg/m2 分2 連日21日間投与 2週休薬、TXLは70ないし80 mg/m2をday 1, 8, 15, 21に60分点滴静注し2週休薬、5週間を1サイクルとした。 全症例のRRは50%だが、前治療のないものでは75%、あるもので45%で、MSTは278日、TTPは146日であった。有害事象については、grade 3以上のものは低頻度だったと報告された。 この結果で、演者はこの併用療法について、feasibilityの高い治療法と述べている。しかし、肝転移には効いておらず、転移巣の大きいものには避けた方がよいとの考えが示された。 楢原啓之ら(大阪府成人病センター消化器内科)の発表は、進行・再発胃癌に対するS-1とTXL併用化学療法の第I/II相臨床試験についてのものだった(OS116-4)。 step Iで S-1/TXLに対するTXLのMTDと推奨用量を求め、step IIで推奨用量を用いた場合のRRを検討している。また各薬剤の血中濃度測定により、両薬剤を併用した場合のpharmacokinetics(PK)も観察されている。 投与方法は、S-1が80 mg/m2 分2を14日間連日投与し、1週休薬。TXLは50, 60, 70, 80 mg/m2の各量をday 1, 8に60分間かけて点滴静注し、1週休薬。この3週間を1サイクルとした。 15日間以上の休薬、もしくはday 8のTXL投与のスキップを臨界毒性とし、これが2/6例に出た投与量をMTDとしたところ、60 mg/m2がMTDと判定された。従って、TXLの推奨用量は50 mg/m2となる。 12症例全体のRRは50.0%だが、推奨用量(50 mg/m2)のTXLを投与した場合のRRは62.5%だった。また薬物血中濃度の解析では、TXL併用の5-FU濃度への影響はみられなかった。 なお、これらはphase IIに登録され、現在その解析中であると報告された。 ここで試みられたTXL 3週投与法は、biweekly投与法に比して効果が高く、毒性が低いことが卵巣癌や肺癌、乳癌などで報告されている。 高橋郁雄ら(九州大学大学院消化器・総合外科)の発表は、前演題(楢原ら OS116-4)のTXL 3週投与に対し、biweekly投与のTXTとS-1を併用した場合のphase I studyであった(OS116-5)。 S-1は80 mg/m2 分2 14日間連日投与で2週休薬、TXTは40 mg/m2から50 mg/m2まで、5 mg/m2ずつdose upしてday 1, 15に点滴投与し、2週休薬、28日間を1サイクルとした。 その結果、S-1/TXTにおけるTXTのMTDは40 mg/m2であった。なお、35 mg/m2で再検討した結果、推奨用量は35 mg/m2となった。主な有害事象は好中球減少で、RRは評価可能例で42.9%と報告された。 S-1/TXLでは、類似の投与スケジュールが複数存在することが問題である。多施設参加の臨床試験で採用するregimenが異なると、同一施設でも複数の投与スケジュールを用いざるを得なくなる。臨床試験の計画をたてる際は、regimenの数を増加させない配慮が必要であろう。 貴重なnegative dataの発表 〜S-1隔日投与法の試み〜 金井陸行ら(田附興風会医学研究所北野病院外科)からは、S-1隔日投与法に関してnegative dataの発表があり(OS112-5)、注目を集めた。 悪性腫瘍細胞は細胞周期が長く、正常細胞は短いとの説に基づいたS-1の新規投与法の検討である。S-1を隔日投与することによって正常細胞はその毒性からescapeできるが、悪性細胞には同等の細胞毒性が期待できるとの仮説が立てられた。 進行胃癌20症例にS-1 80 mg/m2を1日2回隔日投与した。しかし、実際はほとんどの症例がPDとなり、RRは4.3%、MSTは159日で試験中止となった。有害事象としては骨髄抑制がやや少ないが、消化器症状はやや増強していたとのことである。 消化管毒性の増強は、S-1の1回投与量を倍量にしたことに由来すると考えられる。結局、この投与法では臨床効果を激減させて有害事象をむしろ増強させるという、仮説とは正反対の結果が得られた。正常細胞に比較して悪性腫瘍細胞の細胞周期が長いとの報告は、少なくともこの四半世紀はなされていない。悪性腫瘍細胞のdoubling timeが数十日に及ぶ理由としては、G0のfractionが優勢であることや、分裂する一方でアポトーシスが進行するなどの理由が考えられる。 演者は、腫瘍細胞のheterogeneityも考え合わせると、本療法には全く有用性を認めないと述べていた。 さまざまな抗癌剤の投与法が編み出され、そのほとんど全てが有用であると報告されている中で、negative dataを公表した行動は賞賛に値する。科学の世界では、negative dataはpositive dataと同様に貴重なものであることを強調したい。 |
| |前の頁に戻る| |
