 |
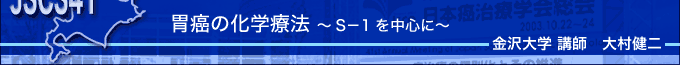 |
| S-1は、胃癌の化学療法において中心的役割を果たす薬剤になることは、もはや疑いのないところである。しかし、さまざまな臨床経験が積まれた結果、S-1では高いresponseが得られる半面、生存期間の延長への寄与が明らかでないことが指摘されていた。S-1は、まだ適切に使用されていない可能性があり、早期に治験を蓄積し、標準的な治療法を確立する必要がある。 本学会では三日目に終日S-1のセッションが組まれ、S-1 based chemotherapyの将来像が垣間見られる発表も数多くなされ、熱心な討論が展開された。 S-1発売前後の化学療法成績の比較 〜進行・再発胃癌〜 平林直樹ら(広島市立安佐市民病院外科)の発表(OS113-2)は、S-1の臨床応用が胃癌の治療に与えた変化を検討したものであった。 stage 4胃癌の治療に関しては、S-1発売以前の1998年にはbest supportive care(BSC)が主流で、化学療法施行は15例中6例に過ぎず、median survival time(MST)も210日だった。一方2001年にはS-1を含む化学療法が主流になっており、21例中18例が化学療法を受け、MSTは467日に延びていた。両年の全症例をあわせると、BSC vs 化学療法では、MSTが118日 vs 520日という結果になった。 ここ数年で、stage 4胃癌に対し化学療法によるQOLの改善や生存の延長が期待できるようになった。そのため医師の化学療法に対する認識も明確に変化した。新しい抗癌剤、とりわけ外来投与可能なS-1の導入は積極的な化学療法を促進し、患者の予後の改善、QOLの向上をもたらしたものと考えられた。 小林理ら(神奈川県立がんセンター消化器外科)の報告(OS113-3)も、前演題(平林ら OS113-2)と同様、S-1がもたらした再発胃癌の治療成績の変化を検討したものだった。 LV/5-FU+CDDP(FLP,79 例)とS-1(33例)をfirst lineとした再発胃癌112例を対象とし、各群の再発後生存期間を比較した。全体のMSTはFLP群212日、S-1群437日だった(p<0.01)。 術前と再発時の血清CEAが正常であった群では、FLPと比較してS-1で有意に生存期間が延長していた(p<0.01、p<0.02)。またPS0症例ではS-1による生存期間の延長傾向がみられるにとどまったが、PS1症例ではFLPと比較してS-1で有意な生存期間の延長がみられた(p=0.04)。MSTは、FLPと比較してS-1で7ヵ月延長していた。 なお、両群間の再発形式に差がないかと質問がなされたが、特に差を認めないとの回答であった。 佐々木徹ら(北里大学東病院消化器内科)の報告(OS113-4)は、S-1単独投与45例と他剤との併用投与32例の計77例を対象に、抗腫瘍効果と安全性を検討した発表であった。 Overallのresponse rate(RR)は53.2%で、原発巣以外の肝転移、リンパ節転移巣などにも50%以上の症例で効果を認めた。S-1単独群に比較すると、他剤併用群でRRが若干高い傾向がみられた。また、有害事象についてはgrade 3の血液毒性が10%以上にみられ、それは他剤併用群で若干高率であった。全例のMSTは441日、TTPが168日、1年生存率52.8%、2年生存率4.3%。 なお、PR例のMSTは455日だが、NC例でも337日であり、抗腫瘍効果より、tumor dormancyの考え方が今後は必要ではないかと述べられていた。cytotoxic agentによって腫瘍の増殖が抑制されている状態をtumor dormancyと称してよいのか疑問である。 矢野友規ら(国立がんセンター東病院消化器内科) は、ASCO2001において切除不能進行胃癌のJCOG臨床試験登録例497症例を解析し、2年生存率は8%、5年生存率は2%であり、長期生存例は腹部リンパ節転移例が多いことなどを発表している。 今回は、S-1の市販後、2年生存者の多くが腹膜播種例であるなど、S-1、CPT-11、Taxaneなどの新薬が臨床応用されて以降、進行胃癌に対する化学療法の長期生存例のprofileが変化しつつあることに着目して検討を行なった(OS76-4)。 対象は、国立がんセンター東病院で'92.8から'01.3までに全身化学療法を施行した症例337例である。それらについて、化学療法の成績をS-1市販の前と後で比較した。全症例の2年生存率は13.3%(5年生存率 2.5%)であった。S-1発売前の226例と発売後の111例を比較すると、MSTは各々8.6ヵ月、11.2ヵ月であった。さらに2年生存率は各々9.3%、21.8%であり、S-1の導入は有意な生存期間の延長をもたらしていた(p=0.0016)。 さらに、S-1発売後の2年生存例には、未分化型が73.9%(発売前38.1%)、腹膜転移例が65.2%(発売前23.8%)含まれており、ともにS-1市販前と比較して有意に増加していた。 口演後の質疑で、S-1やCPT-11などの発売により、2nd line以降のregimenの数が増えたことも長期生存に影響している可能性が指摘された。 胃癌の化学療法が確実に進歩していることは明らかであり、現在その中心にあるのがS-1であることは広く認知されるに至った。また、second line以降の薬剤の寄与するところも大である可能性が高いと思われる。 S-1とCPT-11の併用化学療法 〜進行・再発胃癌〜 山下俊樹ら(東京医科歯科大学食道胃外科)は、切除不能・再発胃癌に対するS-1/CPT-11併用療法の臨床第I/II相試験の成績を発表した(OS113-1)。 切除不能・再発胃癌16例に対してS-1を80 mg/m2/day 2週間とCPT-11をday 1、8に70 mg/m2より開始して投与した。CPT-11の投与量は、70 mg/m2, 80 mg/m2, 90 mg/m2, 100 mg/m2の4段階とし、2週間投与2週間休薬を1サイクルとして、1サイクル終了後に有害事象を検討した。 参考値としてのRRは56%、CPT-11 100 mg/m2でgrade 3以上の血液毒性 1例、下痢 3例を認め、maximum tolerated dose(MTD)に達したとし、推奨用量は80 mg/m2と報告した。 なお、現在phase IIが進行中で2003年6月までに13例がエントリーされ、中間成績はRR 69%、1年生存率 52%、MST 391日とのことであった。 質疑の中で, 腹膜播種の症例は除外していると述べられた。また、この療法でPDになった症例に second lineでS-1/CDDPを行なうと、SDを保てる感触があるとのことであった。 |
| |次の頁へ続く| |
