 |
-支持的な場の設定-
【病名告知】の場面では,1)信頼関係の構築,2)場の設定の2点を考慮する必要があります.
1)患者は検査や診断の結果を聞くため,慣れない病院に不安を抱えて来られている訳ですから,大変緊張をしています.このため,医師は常に礼儀正しく接することを心がけ,とくに初対面の場合は最初に自己紹介をし,挨拶は立って行うようにします.また,話をするときは身体を患者のほうへ向け,目や顔を見ながら行うようにします.しかし,目を凝視することは避けます.
2)プライバシーが保てる面談室などを使い,カーテンで仕切られた程度の外来などでの面談はできるだけ避けるようにします.また【病名告知】の場面は,これから信頼関係を築く段階にあるため,座る位置にも配慮し,適度な距離を図るようにします.
さらに,同席者(家族)がいる場合,【病名告知】は患者だけに伝えるか,同席者にも一緒に伝えて良いか,患者の意向を確認し,患者主体で進めていくようにします.
|
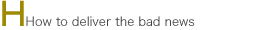 |
-悪い知らせの伝え方-
悪い知らせを伝える前に,病名,これまでの経過,今回の面談の目的などを振り返り,現在の状況に対する患者の認識を確認します.
悪い知らせはすべてを伝えることが原則ですが,具体的にどの程度の情報を伝えるかについては,患者の意向を確認します(とくに余命など).また,伝える際には,明確な言葉を用いるようにします(一度ははっきりと「がん」という言葉を用いるべきですが,繰り返し用いることは避けます).
専門用語は避けるか,専門用語を用いた場合は,理解できているかを確認しながら行います.
一方的に情報を伝えるのではなく,患者や家族に質問を促し,質問には十分答えるようにします.話の進み具合が速すぎないか,気持ちはどうか,患者に質問しながら面談を進めるようにします.
そのほか,いらいらした様子で対応しないことも大切です.いらいらした様子には,貧乏ゆすり,ペンを廻す,患者の言葉を途中で遮るなどがあります. |
 |
-付加的状況-
患者の意向を第一に尊重することを伝えたうえで,今後の治療方針や治療の危険性,副作用情報など医学的情報を伝えるほか,患者の日常生活や仕事など社会的情報についても説明をします.その際,「何か疑問に思うことがあれば,いつでもおっしゃってください」といった言葉をかけ,病気についてだけでなく,いつでもどんな話題でも医師が取り上げる(話を聞く)準備があることを伝えると良いでしょう. |
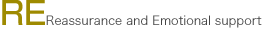 |
-安心感と情緒的サポート-
【病名告知】をする際は,患者が医師の言葉を受け入れる心の準備ができるよう,言葉(「お話してもよろしいですか」,「残念ですが・・・」など)や間をとるようにし,いきなり病名を告げることは避けるようにします. 病名を告げたあと,患者が感情を表に出してもそれを受け止めるようにします.沈黙の時間をとる,患者の次の一言を待つ,患者の気持ちを自分の言葉で言い換えるといった言動を通じ,患者への共感(やさしさ,思いやり)を示します.「ご心配なことは何ですか」など,オープン・クエスチョンを用いて患者の気持ちを理解するほか,患者の家族に対しても共感や理解を示すようにします. |
