 |
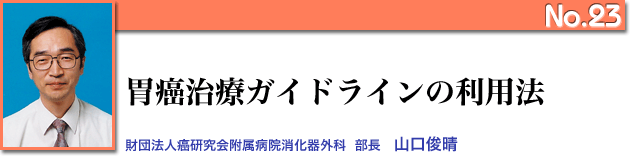 |
�͂��߂� / �݊����ÃK�C�h���C���̍쐬�v���Z�X
/ �K�C�h���C����EBM / ��t�p�K�C�h���C���̗��p�@ /�@
��ʗp�K�C�h���C���̗��p�@
/ ������ |
| �͂��߂� |
| |
�@1962�N����݊�������͈݊���舵���K����쐬���A���Ð��т̉Ȋw�I��r���\�ɂ���Ƌ��ɁA�݊����Â̕W�����ɐs�����Ă����B���̌��ʁA�킪���ɂ�����݊��f�Â͐��E�ō����x���ɂ܂ŒB�����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B���̈݊���舵���K��ɏK���A�咰��������ȂǑ����̊���舵���K���w�����\����Ă���͎̂��m�̒ʂ�ł���B��������ꂸ�Ɍ����ƁA�݊���舵���K��͑�2�Q�܂ł̃����p�ߊs���iD2�s���j���S�[���h�X�^���_�[�h�Ƃ����A����Ύ��ÃK�C�h���C���̑��ʂ����悤�ɂȂ��Ă����B���Õ��j�͎���Ƌ��ɕϑJ������̂ł���AD2�s����������ׂ��Ƃ����O��ɗ�����������Ƃ́A��舵���K��̕p�ɂȉ�����]�V�Ȃ����ꂽ�B
�@ 1998�N�ɓ��{�݊��w��ݗ�����ĊԂ��Ȃ��A�݊����ÃK�C�h���C���̍쐬�Ɍ����Č������J�n���ꂽ�B����́A�݊�������𒆐S�Ƃ����킪���̖c��Ȉ݊��f�ÂɊւ���Ɛт����A�݊��̃X�e�[�W�ʂ̕W���I���Â��������Ƃ������̂ł���B�܂�A�݊���舵���K��A���ÃK�C�h���C���I�ȗv�f�m�ɕ������悤�Ƃ��鎎�݂ł������B2001�N3���ɂ͈݊����ÃK�C�h���C�������s����1�j�A2004�N4���ɂ͉�����2�ł����s���ꂽ2�j�B�܂��A2001�N12���ɂ͈�ʗp�Ƃ��āA�݊����ÃK�C�h���C���̉�������s����Ă���i�}1�j3�j�B�{�e�ł͈݊����ÃK�C�h���C���̍쐬�ߒ����Љ��Ƌ��ɁA�K�C�h���C���̗��p�ɂ������ė��ӂ��ׂ��_���q�ׂ�B |
| �}1 ��ʗp�K�C�h���C���\�� |
| |
|
| |
�����̃y�[�W�̃g�b�v�� |
| �݊����ÃK�C�h���C���̍쐬�v���Z�X |
| |
�@���{�݊��w��̈݊����ÃK�C�h���C�������ψ����̂ƂȂ��āA�K�C�h���C���͍쐬����Ă���B���̈ψ���́A�݊���舵���K�����������K��ψ���Ƃ͑S���ʂ̑g�D�ł���A�쐬�ψ���ƕ]���ψ���ɕ�����Ă���B�]���ψ���͑g�D�I�ɂ͍쐬�ψ���Ƃ͑S���قȂ����@�\�ƌ��������ψ���ł���A�쐬�ψ���ɂ���č��ꂽ�K�C�h���C�����Ă�Ǝ��̎��_���猟���]������B�܂��A�쐬�ψ���ƕ]���ψ���̍��ӂ�����ꂽ�K�C�h���C�����ẮA�݊��w�����ɂ����čX�Ɍ��������B�����āA�ŏI�Ă͓��{�݊��w��S����ɔz�z���ꂽ�̂��A�w��̑���ŃR���Z���T�X�~�[�e�B���O���J�Â��A�_�c��s��������Ő����̃K�C�h���C���Ƃ��Č��\�����B
�@ ���̂悤�Ȏd�g�͈ꌩ�ώG�̂悤�ł��邪�A�ꕔ�̈ψ��̎v�����݂��ς��ɗ͔r�����邽�߂ɕK�{�̃v���Z�X�ł���i�}2�j�B���ł̃K�C�h���C���ɂ��ẮA���{�����Êw���ł����̊����w��̑�\�������ĕ]�������B�܂��A���ÃK�C�h���C���͖{����t�p�ɍ쐬���ꂽ���̂ł͂��邪�A�K�C�h���C���̓��e���L�����҂�����ʂ̕��ɗ��������ׂ��ł���Ƃ����l������A�݊����ÃK�C�h���C���̉�����쐬���J���ꂽ�B |
| �}2 �K�C�h���C���쐬�v���Z�X |
| |
|
| |
�����̃y�[�W�̃g�b�v�� |
| �K�C�h���C����EBM |
| |
�@�݊����ÃK�C�h���C���쐬�ɂ������Ă̊�{���j�́AEvidence Based Medicine�iEBM�j�ɑ���Ƃ������Ƃł������B�ŋ߂͎��m�̂悤�ɁA���Ö@�������ۂɂ̓G�r�f���X���x���i�\1�j�������悤�ɋ��߂��Ă���B�������A�݊����ÂɊւ���EBM�͕K�������L�x�ɂ���킯�ł͂Ȃ����Ƃ��\�z���ꂽ�B�����ŁA�쐬�ψ���ł͂킪���Ō��ݍs���Ă���݊����Â̎��Ԃ�m�邽�߂ɁA���{�݊��w������ΏۂɍL�͂ȃA���P�[�g���������{�����B���Ɉ݊����ÂɊւ��Đ��E�ō��̎��т����킪���Ō����ɍs���Ă����Â̎��ۂ́A�K�C�h���C���쐬�̏�ŏd�v�����ꂽ�B
�@ ���̂悤�Ȍo�܂���A�o���オ�����K�C�h���C�����T�|�[�g���镶���I��EBM �͏\���Ƃ͌����Ȃ��B�������A���ԂɊ�Â����K�C�h���C���̌��J�ɂ͂���Ȃ�̈Ӌ`������A������@�ɉȊw�I�ȗՏ������̐ςݏd�˂ɂ��AEBM�����グ�ăK�C�h���C�����������čs���p�����A��X�Ɋ��҂���Ă���ƌ����悤�B |
| �\1 �G�r�f���X���x�� |
| |
 |
| AHCPR�iAgency for Health Care Policy and
Research�j�ɂ��؋��]��� |
| I a |
�������r�����̃��^�A�i���V�X |
| I b |
���Ȃ��Ƃ��ЂƂ̖�������� |
| II a |
���Ȃ��Ƃ��ЂƂ̗ǂ��f�U�C�����ꂽ������� |
| II b |
���Ȃ��Ƃ��ЂƂ̑��̃^�C�v�̗ǂ��f�U�C�����ꂽ�������I���� |
| III |
��r�����A�������A�Ǘ��r�����ȂǁA
�悭�f�U�C�����ꂽ������I�L�q�I���� |
| IV |
���Ƃ̈ψ����̕�ӌ��A���Ў҂̗Տ��o���Ȃ� |
|
 |
|
| |
�����̃y�[�W�̃g�b�v�� |
| ��t�p�K�C�h���C���̗��p�@ |
| |
�@�K�C�h���C���̍��q�́A�X�e�[�W�ʂɓ���f�ÂƂ��ĕW���I�Ȏ��Ö@���������Ƃɂ��邪�i�\2�j�A�����Ɍ��ݗՏ������Ƃ��čs���Ă��鎡�Ö@�ɂ��Ă������i�\3�j�B����f�ÂƗՏ������̖��m�ȋ�ʂ͕K�������e�Ղł͂Ȃ����A����2����ʂ��邱�Ƃɔ��̈ӌ������������A���̊Ԃ������܂��ɂ����܂܂ł̓K�C�h���C���̈Ӌ`���傫�����Ȃ���ƍl����ꂽ�B�������A�Տ������Ƃ��ĔM�S�Ɍ�������āA���̐��ʂ����炩�ɂȂ����ꍇ�ɂ́A�Տ������������f�ÂւƔF�����ς�邱�ƂɂȂ�B����f�ÂƂ��Ď����ꂽ�p���⎡�Ö@�̑Ó���������EBM�́A���ɊO�Ȏ��Âŏ��Ȃ��ɂ�������炸�A�R���Z���T�X��͔̂�r�I�e�Ղł������B�݊�������ォ��̎��тŁA�O�Ȉ㑊�݂̗�����������x�m������Ă����Ƃ����������傫�������B
�@ ����A���w�Ö@�Ɋւ��ẮAEBM�������ł͂��邪�F�߂��Љ��Ă���B2001�N�̏��łł́A��p�s�\�i�s����Ĕ����ɂ����鉻�w�Ö@�̈Ӌ`��F�m�������̂́A��̓I�ɐ�������郌�W���������ꂸ�A��2��3�j�ł͌��ݐi�s���̗Տ���3���������������Љ�Ă��̃��W�����������B
�@ �K�C�h���C������O�ꂽ���Õ��j���ւ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B���҂���̃��X�N���]�ɉ����čŏI�I�Ɍ��肳�����̂ł���B�܂��A�⏕���w�Ö@��g�僊���p�ߊs���͓���f�ÂƂ��ĔF�m����Ȃ��������A�e�{�݂̔��f�Ɗ��҂���̗����̏�ŁA�����̎��Ö@��I�����鎖���\�ł���B�������A�����ɂ������Ă̓K�C�h���C���ɂ�����f�Â������ŁA�Ȃ��قȂ������j�𐄏�����̂��\���ɐ�������`�������邱�Ƃ𗝉�����K�v������B�����āA����f�Â���O�ꂽ���Â̑������Տ������Ƃ��čs���A�����̎��݂����̎��Ö@�̕]���ɂȂ���悤�ȑ̐��ɂȂ�A�킪���̈݊����Ẫ��x���͊i�i�Ɍ��シ��Ɗ��҂����B |
| �\2 �X�e�[�W�ʂ̈݊��̓���f�f |
| |
 |
| |
N0 |
N1 |
N2 |
N3 |
| T1(M) |
IA
EMR�i�ꊇ�؏��j
�@�i�����^, 2.0cm�ȉ�,
�@���^�ł�UL�i�|�j�j
�k����pA1�j
�@�i��L�ȊO�j |
IB
�k����pB1�j
�@�i2.0cm�ȉ��j
��^��p
�@�i2.1cm�ȏ�j |
II
��^��p
|
IV
�g���p
�ɘa��p
�i�Ƒ���p�j
���w�Ö@
���ː�����
�ɘa��� |
| T1(SM) |
IA
�k����pA
�@�i�����^, 1.5cm�ȉ��j
�k����pB
�@�i��L�ȊO�j |
| T2 |
IB
��^��p2�j |
II
��^��p |
IIIA
��^��p |
| T3 |
II
��^��p |
IIIA
��^��p |
IIIB
��^��p |
| T4 |
IIIA
�g���p�i���j3�j |
IIIB
�g���p�i���j |
|
|
H1,P1,
CY1,M1,
�Ĕ� |
|
|
|
 |
| 1�j |
�k����pA, B�F��^�I�؏����݂�2/3�ȏ�؏��Ƃ����, ���ꖢ���̐؏����k���؏��Ƃ���B
option�Ƃ��đ�ԉ���, �ԔX�؏��̏ȗ�, �H��ۑ��ݐ؏��iPPG�j, �����_�o�����p�Ȃǂ{����B
�܂������p�ߊs���̒��x�ɂ��k����pA�iD1�{���j�Ək����pB�iD1�{���j�ɂ킯���B
���̊s�����ʁF���ʂɂ�����炸No.7, �܂��a�ς������ɂ���ꍇ�͂����No.8a��lj�����B
���̊s�����ʁFNo.7, 8a, 9���s������B |
| 2�j |
��^��p�F�݂�2/3�ȏ�؏���D2�s�� |
| 3�j |
�g���p�i���j�F��^��p�{�����퍇���؏� |
| 4�j |
Stage�ʂ̎�p�@�͏p���̓���ɂ��Stage�Ɋ�Â������̂ł���,
�k����p�̓K���ɂ����ċ^��̗]�n������ꍇ�͒�^��p�����߂���B |
|
 |
|
| �\3 �X�e�[�W�ʂ̈݊��̗Տ����� |
| |
 |
| |
N0 |
N1 |
N2 |
N3 |
T1(M)
��2.0���� |
IA
EMR�i�����؏��j
EMR�i�؊J�����@�j
EMR �s���S��ɑ�
���郌�[�U�[���ÂȂ� |
IB
���o���⏕���؏� |
II |
�W
�g���p
�@�i���E�s���j
���ʎ�p
���w�Ö@
�@�i�S�g�E�Ǐ��j
���M���w�Ö@ |
| T1(SM) |
IA
�Ǐ��E���ߐ؏�
���o�����Ǐ��؏�
���o���⏕���؏� |
| T2 |
IB
���o���⏕���؏� |
II
�p��⏕���w�Ö@ |
IIIA
�p��⏕���w�Ö@ |
| T3 |
II
�p��⏕���w�Ö@
�p�O���w�Ö@ |
IIIA
�g���p�i�s���j1�j
�p��⏕���w�Ö@
�p�O���w�Ö@ |
IIIB
�g���p�i�s���j
�p��⏕���w�Ö@
�p�O���w�Ö@ |
| T4 |
IIIA
���w�Ö@
�p�O���w�Ö@
�p��⏕���w�Ö@
���ː��Ö@ |
IIIB
�g���p�i���E�s���j1�j
���w�Ö@
�p�O���w�Ö@
�p��⏕���w�Ö@ |
|
|
H1,P1,
CY1,M1,
�Ĕ� |
|
|
|
 |
| 1�j |
�g���p�i�s���j�F�g�僊���p�ߊs�����Ӑ}�����g���p�B
�g���p�i���E�s���j�F�����퍇���؏��Ɗg��s�����s���g���p�B |
|
 |
|
| |
�����̃y�[�W�̃g�b�v�� |
| ��ʗp�K�C�h���C���̗��p�@ |
| |
�@��ʗp�K�C�h���C���̓Z���t�K�C�h�u�b�N�ł͂Ȃ��B�܂�A���҂���₻�̉Ƒ����ǂނ����Ŏ����I�Ɏ��Ö@�����܂�悤�ȃ}�j���A���{�ł͂Ȃ��B�Ƃ��ɂ́A���҂����@�����ۂɉ��̐����������K�C�h���C����n���āA��x�ʓǂ��Ă�����Ă����t���������J�n����悤�ȗ��p�@���s���Ă��邪�A����͐��������p�@�Ƃ͌����Ȃ��B��ʗp�K�C�h���C���̕\���ɂ́A�K�C�h���C�������̏�ɊJ���A���҂���Ƃ��̉Ƒ��ƈꏏ�Ɉ�t�������Ă���G���ڂ����Ă���i�}1�j�B�K�C�h���C���Ƃ͈�t�̐������Ȃ����̂ł͂Ȃ��A���̊G�̂悤�Ɉ�t�̐��������ǂ����������邽�߂̂��̂ł���B
�@ �݊��ł��邱�Ƃ�鍐������ɁA������ڍׂɕa��i�X�e�[�W�j�⎡�Ö@�ɂ��Đ������Ă��A���̍��m�������҂�����S�ň�t�̐��������Ƃ͂�������ł���B���̂悤�ȏꍇ�ɁA���҂��A���ɃK�C�h���C���𗘗p���邱�ƂŁA���߂Ĉ�t�̐����ɑ��闝����[�߂邱�Ƃ��\�ɂȂ�B��ʗp�K�C�h���C���ɂ́A�X�e�[�W�ʂ̎��Ö@�����������łȂ��A�݂̐������U�Ɋւ���m���A�݊��̊�{�I�m���ɂ��Ă��T�����Ă���B���̕����́A��t�̐����̒��ŕs�\���ɂȂ�Ղ������ł�����B�܂��A���҂���̗�����e�Ղɂ��邽�߂ɊG���o������葽���̗p�����i�}3�j�B���݁A�������ꂽ��2�łɉ����āA��ʗp�K�C�h���C���̉�����Ƃ��i�s���ł��邪�A�G�͍X�ɑ��₳���\��ł���B�O���łǂ̂悤�ɒ��J�ɐ��������Ƃ��Ă��A��������ɂ���������A�����Ύ��₳��鎖���́AQ��A
�Ƃ��Ď����҂̒��ɂ܂Ƃ߂��Ă���B���̌�̌����ōX�ɂ��̍��ڂ����₳���\��ł���B
�@ �݊��̎��ÃK�C�h���C�������J����Ă���A��ʗp�K�C�h���C���Ɋւ��Ă͈�t����łȂ��R���f�B�J���X�^�b�t�⊳�҂���Ƃ��̉Ƒ��̕�����A�����̋M�d�Ȉӌ��������������B��t����͕��G�߂���̂ł��������Ȍ��ɂƂ����ӌ��������������A���҂���̃T�C�h����͂��ڍׂɂƂ�����]�����Ȃ��Ȃ��B�m���ɁA��ʗp�K�C�h���C�������ׂĐ������悤�Ƃ���ƁA���Ȃ��Ƃ�1���Ԉȏォ����B���̐�����v���ɂ��邽�߂Ƀt���[�`���[�g�̓�������Ă���Ă���A�������ł���B��ʗp�K�C�h���C���̗v����p���t���b�g�ɂ��Č����̏�Ŕz�z����ׂ��Ƃ����ӌ�������B��������X���ɒl����ӌ��ł���B��ʗp�K�C�h���C���ɂ͗���ɂ���Ă��܂��܂ȑ��ʂ�����A����Ӗ��ň�t�p�K�C�h���C�����쐬�͓���A���ׂĂ̈ӌ����������͕̂s�\�̂悤�Ɏv����B��ʗp�K�C�h���C�����쐬���Ă���̂͊��̕���ł͈݊������ł���A���ꂩ��ǂ̂悤�ɉ��������̂����ڂ����B |
| �}3 ��ʗp�K�C�h���C���̊G�i�݂��ÃK�C�h���C���̉���m��ʗp2001�N12���Łn�����o�Łj |
| |
|
| |
�����̃y�[�W�̃g�b�v�� |
| ������ |
| |
�@�����ÃK�C�h���C�����쐬����ɂ������čł��������Έӌ��́A�u��t�̍ٗʌ����N�����i���R�Ȑf�Â��o���Ȃ��j�v�A�u�K�C�h���C�����O���Ƒi������v�A�u�V�����i�����Ȃ��Ȃ�v�A��3�ɏW���B���������A��t�̍ٗʌ��Ƃ͂ǂ̂悤�Ȏ��Â���t������ɏo����Ƃ������̂ł͂Ȃ��A��t�̏\���Ȑ����̂��ƂɊ��҂����玡�Õ��j�����肵�A����ɂ��������Đf�Â��s����ׂ��ł���B�����āA���̐����ɂ͈��̃��[�������߂��Ă���B
�@ �܂��A�K�C�h���C���Ɋ�Â��W���I���Â���������ŁA�Ȃ��قȂ������Â��s����̂��\���Ȑ���������Ζ�肪�N����\���͂ނ���Ⴂ�B�����āA�W���I�Ȏ��ÂƈقȂ�ӗ~�I�Ȏ��Â��A�Տ������Ƃ��Ă��̐��ʂ���Â̐i���ɂȂ���`�Ŏ��H���A���҂���ɂ��ϋɓI�ɎQ�����Ă��炤���ƂŁA�ނ����Â̐i���͑��i�������̂Ɗm�M���Ă���B
�@ ���̂悤�Ȏ��ÃK�C�h���C���͊w����Ƃ⍑�Ƃ̎v�f�Ƃ͈�������R�ȗ���ō쐬�����ׂ��ł���A�쐬�ψ��̒���I���A�w��̐i���ɔ�������I�����A�O������̕]���̎���ȂNJ܂߁A���̍쐬�ߒ��ɂ��ڂ�������K�v������B�����āA�K�C�h���C�����^�ɖ𗧂��ۂ��́A�܂��ɂ���𗘗p����҂����̃K�C�h���C���ɑ��闝��x�ɂ������Ă���B |
| |
|
| �Q�l���� |
| |
| 1�j |
�݊����ÃK�C�h���C����t�p2001�N3���ŁA
���{�݊��w��ҁA�����o�Ŋ�����ЁA�����A2001 |
| 2�j |
�݊����ÃK�C�h���C����t�p2004�N4�������m��2�Łn�A
���{�݊��w��ҁA�����o�Ŋ�����ЁA�����A2004 |
| 3�j |
�݂��ÃK�C�h���C���̉���m��ʗp2001�N12���Łn
�\�݂��Â𗝉����悤�Ƃ��邷�ׂĂ̕��̂��߂ɁA
���{�݊��w��ҁA�����o�Ŋ�����ЁA�����A2001 |
|
| |
2004�N10�����s |

