 |
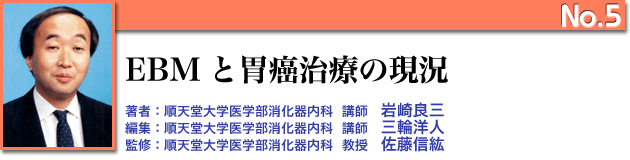 |
| 緒言 / 早期胃癌 / 切除可能進行胃癌
/ 切除不能進行胃癌 / まとめ |
| 緒言 |
| |
わが国における胃癌治療は近年その治療法の多様化により、治療法の選択肢が増加してきた。例えば、早期癌に対しては内視鏡的粘膜切除術(EMR)、内視鏡的レーザー焼灼術、腹腔鏡下切除術、縮小手術などがあり、進行癌に対しては拡大手術、術前化学療法や多剤併用化学療法などが従来の標準的治療に加わり、癌の進行度に応じた治療法(表1)が施行されるようになってきた。それにより、施設間あるいは同一施設でも医師個人により治療法の選択が異なる場合が生じてきた。そのため、日本胃癌学会では治療法自体に制約を加えるべきではないが、成功率の低い治療を廃し、治療成果を上げるためにも、医師が参考にすべきEvidence
Based Medicine(EBM)に基づく治療ガイドラインとして他学会に先駆けて、2001年3月『胃癌治療ガイドライン』を作成し公開した。本稿ではこの『胃癌治療ガイドライン』を踏まえて、胃癌治療の現況を述べてみたい。
|
| 表1.胃癌の治療法別適応(クリックすると拡大表示されます。) |
| |
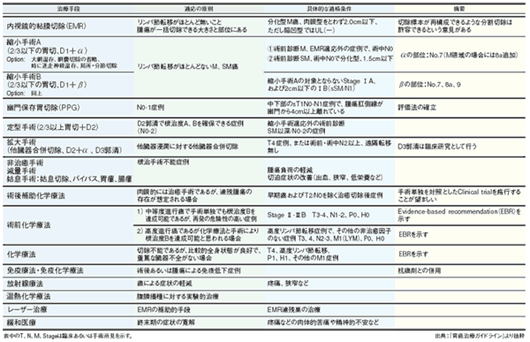 |
| |
▲このページのトップへ |
| 早期胃癌 |
| |
早期胃癌の治療法には内視鏡的粘膜切除術(EMR)、内視鏡的レーザー焼灼術、腹腔鏡下切除術、縮小手術、定型手術などがある。癌の大きさ、その部位、組織型、M癌かSM癌、リンパ節転移の有無、年齢や基礎疾患などによっても、その治療法の選択は異なる。
1)内視鏡的粘膜切除術(EMR)
内視鏡的粘膜切除術の選択には癌の大きさ、予想される深達度、組織型に関する情報が不可欠である。適応は本来、手術により完全治癒が期待される症例であり、リンパ節転移(図1〜3)の可能性がほとんどなく、癌が一括切除できる大きさと部位にあることが望ましい。絶対的な適応条件は2cm以下の分化型の肉眼的粘膜癌と診断された隆起型病変または1cm以下の陥凹型病変でUL(−)に限るが、その完全切除率は83〜96%である。最近では分化型の大きなM癌やSM癌、低分化型癌にもEMRの適応拡大による拡大EMR(ITナイフ法など)が施行されているが、SM癌のリンパ節転移が5.6〜16%(図2、3)に認められることから、SM癌における適応拡大は今後も慎重な検討が必要と考えられている。EMR後の再発率は4.2〜22.3%みられ、再発治療として再EMR施行(47.3%)の次に胃切除術(24.0%)が多くみられており、十分なインフォームド・コンセントのもとで治療法を選択することが大切である。
2)縮小手術・局所切除術(腹腔鏡下または開腹)
早期胃癌の中でもEMRの適応とならない大きさや部位に病変があった場合、通常の定型胃切除術(2/3以上の切除範囲とD2郭清)だけでなく、切除範囲の縮小手術が施行されたり、非開腹下手術である腹腔鏡下で外科的に局所切除が施行されることも多くなってきた。縮小手術、局所切除術などの治療法の選択にあたっては超音波内視鏡などによる深達度診断が必要と考えられる。また噴門部・胃体上部の胃癌に対しては噴門側胃切除術、胃角部の胃癌に対しては幽門温存胃切除術が試みられることも多い。これらの縮小手術、局所切除術は術後合併症の減少という観点からは有用であるが、機能温存とリンパ節郭清とのバランスなどを含めた検討が必要である。特に腹腔鏡下の局所切除術はEMRと縮小手術の中間に位置づけられる手術法で、腫瘍の局所切除または腫瘍を含む胃の分節切除と近傍のリンパ節切除(D1+α郭清)を含むものであるが、今後Evidenceの確立のために症例を積むことが必要である。本法は施設によっては日帰り手術も可能であり、在院日数の短縮もはかれることから、患者のQOL(Quality
of Life)の向上やcost-benefitの観点からも癌の根治性とのバランスを考慮して、今後の発展を期待したい。 |
| 図1. 肉眼的M癌(sM)のリンパ節転移頻度(%) |
| |
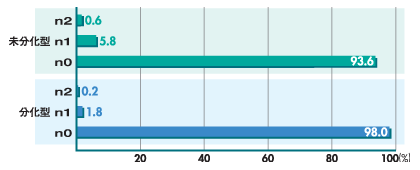 |
| 図2. 肉眼的SM癌のリンパ節転移頻度(%) |
| |
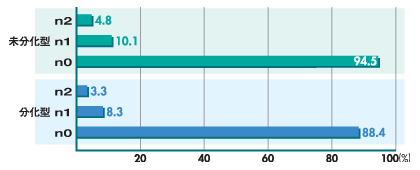 |
| 図3. 組織学的SM癌のリンパ節転移頻度(%) |
| |
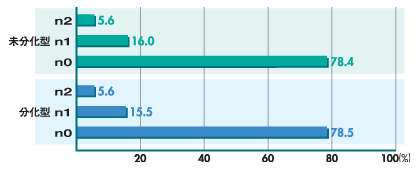 |
| |
注)
n0:リンパ節転移のないもの
n1:1群リンパ節転移を認めるもの
n2:2群リンパ節転移を認めるもの
出典:『胃癌治療ガイドライン』を改訂・引用 |
| |
▲このページのトップへ |
| 切除可能進行胃癌 |
| |
進行胃癌に対して、我が国で安全かつ有効な標準治療法として確立されている定型手術(胃2/3以上切除とD2リンパ節郭清)(表2)は、欧米では重篤な合併症への懸念などから限定された施設でしか施行されておらず、胃癌治療の先進国である我が国と欧米の外科医の考え方に大きな隔たりがある。欧米ではリンパ節郭清比較試験の報告はあるが、我が国ではそのような比較試験の報告はない。
1)D1郭清術とD2郭清術比較試験
定型手術の有効性を確認する欧米での1986年の胃癌手術D1郭清術とD2郭清術の比較試験(n=400)では両群とも予後に差はなく、D2郭清術は在院死亡、術後合併症、入院期間などの点で、D1郭清術より有意に劣っていた。1987年の胃癌(肉眼的治癒切除)手術D1郭清術とD2郭清術の比較試験(n=55)でもD2郭清術は生存率、手術時間、輸血量、入院日数などの点で、D1郭清術より有意に劣っていた。ただこれらの比較試験では症例の割付、外科医のD2郭清術の経験の少なさなどの問題があり、再検討が必要となった。そこで、我が国の協力のもとオランダで1989年に胃癌手術D1郭清術とD2郭清術の比較試験(n=1078)が始まったが、両群とも予後に差はなく、D2郭清術は在院死亡、術後合併症、入院期間などの点で、D1郭清術より有意に劣っていることが再確認された。このリンパ節郭清比較試験の結果のみで、長年にわたりつちかわれた手術手技や術後管理など我が国の定型手術が完全に否定されるわけではないが、定型手術はEvidenceに基づかない標準治療と位置づけられる可能性がある。
2)拡大手術
定型手術の有用性に関してのEvidenceがない現段階ではExperience Basedに施行されてきたD3やD4リンパ節郭清術に関しては、なおさらその有用性についてのEvidenceはない。ただ、拡大手術の恩恵を受けうる患者も少なからず存在する可能性があるが、その選択および治療についてのEvidenceを得る必要がある。 |
| 表2. 定型手術(D2郭清)後のStage別 ※累積5年生存率(%)
n=4494 |
| |
 |
| Stage |
症例数 |
% |
| I A
|
2030 |
93.4 |
| I B |
725 |
87.0 |
| II |
541 |
68.3 |
| III
A |
485 |
50.1 |
| III
B |
273 |
30.8 |
| IV |
440 |
16.6 |
|
 |
|
| |
出典:『胃癌治療ガイドライン』を改訂・引用 ※胃癌取扱い規約第12版 |
| |
▲このページのトップへ |
| 切除不能進行胃癌 |
| |
1)化学療法と無治療(BSC:best supportive
care)
欧米では切除不能進行胃癌(PS0〜2)における化学療法と無治療との比較試験が多数行われている。化学療法としてはMTX/5-FU+ADM、LV/5-FU+VP-16などが施行され、化学療法群(MST9〜12M)が無治療群(MST3〜4M)に比較して有意に生存期間が長く、化学療法の有用性が示されている。わが国ではこのような比較試験はないが、化学療法拒否例でのMSTが3.9Mであったという報告から、切除不能進行胃癌(PS0〜2)における無治療の生存は3〜4ヵ月と考えられた。
2)第III相比較試験
どの化学療法が標準治療となるかを決めるためには、本来、第III相比較試験が必要であり、欧米およびわが国でもその報告がなされているが、有意差が認められた比較試験は少ない。欧米では1991年のFAMTX療法とFAM療法の比較試験(n=208)ではFAMTX療法は奏効率(41%
vs 9%)、MST(10.5M vs 7.2M)とも有意に優れていたが、わが国の追試では有害反応としてGrade4の骨髄抑制が多発したため、FAMTX療法はわが国の標準治療には適さないと考えられた。また、わが国の1991年のFTM療法とUFTM療法の比較試験(n=169)ではUFTM療法は奏効率(7.8%vs25.3%)が有意に優れていたが、MST(6Mvs6M)は変わらなかった。1999年のUFTM療法とFP療法と5-FU単独療法の比較試験(n=280)では奏効率(9%vs34%vs10%)はFP療法が有意に優れていたが、MST(6.4Mvs7.7Mvs7.7M)では変わらなかった。
3)FP(5-FU/CDDP)療法
1999年に日本胃癌学会が『胃癌治療ガイドライン』を作成するためにFirst lineのアンケート調査を行ったところ、第一位のFP(5-FU/CDDP)療法が64%と、第二位のMTX/5-FU
交代療法の15%を大きく離していた。このことから、わが国ではFP療法が最も行われている治療法であることがわかった。しかし、わが国におけるFP療法とその変法であるlow
dose FP療法の報告は第II相比較試験が多く、症例数も9〜55と少なく、奏効率は31〜80%、MST4.5〜10.3Mと、MSTの有意な延長が認められず、FP療法を優れた治療法と認定することは困難であった。わが国で最も行われているFP療法やlow
dose FP療法は残念ながら現状では必ずしもEBMに基づく治療法とは言えず、さらなる大規模第III相比較試験を行うか、CPT-11、TS-1、タキサン系などの新規抗癌剤や、l-LVを併用したレジメンとの比較試験による標準治療の確立が必要である。 |
| |
▲このページのトップへ |
| まとめ |
| |
わが国は胃癌の多発国であり、胃癌の死亡数は年間約5万人で、全癌の約20%を占めている。また胃癌は40〜60歳代に好発し、働き盛りの男性の発症が女性のおよそ2倍といわれていることから社会的打撃も大きい。それにも関わらず、胃癌の標準的治療として知られていたのは胃定型切除術(広範囲切除+D2郭清)のみで、最近の胃癌の病態の多様化、患者のQOLの向上には対応しきれなくなった。また胃癌治療における施設の治療法の相違、治療成績の施設間格差がこの情報化社会で明らかになってきたが、この胃癌治療ガイドラインの登場で少しでも治療成績が上がり、標準化されることが期待されている。
しかし、注意しなくてはならないのは、この胃癌治療が必ずしもEBMに基づいているわけではないこと、またEBMの明らかでない病態や患者がいることである。近年、患者本人へ積極的に癌告知(インフォームド・コンセント)が行われるようになってきているが、現場の医師は常に治療法の選択にあたっては、患者個々の年齢、全身状態、癌の拡がりを把握し、患者と共に『胃癌治療ガイドライン』やEvidenceを参照の上、相互に理解することが望ましい。その上で、このガイドラインに示した適応やEvidenceとは異なる治療を選択する場合には医師は、患者に「なぜガイドラインやEvidenceとは異なる治療を選択する必要があるのか」を説明し、患者の理解を得た上で、オーダーメイド治療を行う必要がある。 |
| |
2001年11月発行 |

