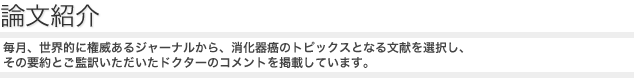12月監修:愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部 医長 谷口 浩也
大腸癌
切除後stage II結腸癌におけるctDNAの解析
Tie J, et al.: Sci Transl Med. 8(346): 346ra92, 2016
Stage II結腸癌患者は手術のみで約80%が治癒するが1)、切除後のマネジメントは定まっていない。Stage II結腸癌における臨床病理学的な再発リスク因子には、T4浸潤、腸穿孔/閉塞発症、不充分なリンパ節郭清、低分化型、リンパ管浸潤などが高リスク因子となることや2,3)、DNAミスマッチ修復機能欠損(dMMR)例が術後化学療法の利益が得られない再発低リスク群であることが報告されている4,5)。また、最近では複数の遺伝子発現を組み合わせたgene signatureが予後に影響を及ぼすことが示されている6-9)。これら臨床病理学的因子や遺伝子発現パターンに基づいた高リスクstage II患者に対する術後補助化学療法がOSを改善することが示唆されているが10-14)、Stage II結腸癌全体では再発リスクが低いため、ベネフィットの検証には大規模な試験が必要であり、より有用なマーカーが求められる。
大腸癌組織には高頻度に腫瘍特異的遺伝子変異15,16)が認められる。切除不能進行・再発大腸癌患者では、末梢血内に血中循環腫瘍DNA(ctDNA)が検出可能であり、非侵襲的に治療による遺伝子変化などの同定が可能である17-20)。また、ctDNAは半減期が2時間以内と短いため21)、ctDNA量の早期減少は腫瘍サイズの有用な動的マーカーとなり22)、治癒切除後の患者の微小転移検出に利用できる可能性が示唆されている21,23,24)。
今回、stage II結腸癌患者を対象に、術後ctDNA statusが微小残存病変の指標として有用かどうか、従来の放射線学的方法による再発患者を同定できるか、を明らかにする前向きのバイオマーカー試験の結果が報告された。
本試験は、豪州の13施設による多施設共同試験であり、必要症例数およびイベント数は、stage II結腸癌患者250例中35例が最初の3年間で再発をするとの予想のもと決定された。血液検体は手術後4〜10週間で収集され、連続した血液検体が3ヵ月ごとに2年まで収集された。術後補助化学療法の使用は治療医の裁量で行われ、ctDNA status結果は盲検化された。また、臨床レビューおよびCEAは3ヵ月ごと、CT撮影は6ヵ月ごとに2年間行われた。主要評価項目は、標準的な放射線学的方法によって評価されたRFS(recurrence-free survival)であった。
2011年7月〜2014年9月の間に、登録例250例のうち適格例231例から1,047の血漿検体が収集された。切除原発腫瘍組織を超並列シーケンサーで分析したところ、231例中230例(99.6%)から1つ以上の体細胞変異が認められた。これら230例の評価可能患者から手術後4〜10週で血液サンプルを採取し、20例(8.7%)で腫瘍特異的変異が検出された(ctDNA陽性)。評価可能230例の患者背景は、年齢中央値65歳、男性57%、右側結腸45%、低分化癌16%、T4浸潤17%、検索リンパ節個数12個未満13%、脈管侵襲あり19%、dMMR18%、臨床病理学的高リスク37%であった(臨床病理学的高リスク患者はDNAミスマッチ修復良好(pMMR)で、T4、リンパ節検索子数12未満、リンパ管侵襲陽性、低分化腫瘍のいずれかの因子を持つものと定義)。術後補助化学療法を施行した52例(23%)は、より若く、1つ以上の高リスク因子を有する傾向にあった。また、術後ctDNA statusと従来の高リスク因子との間に有意な相関は認めなかった。追跡期間中央値27ヵ月(2〜52ヵ月)において、術後補助化学療法を未施行の178例中27例(15%)および術後補助化学療法を施行した52例中7例(13%)に再発を認めた。
術後補助化学療法未施行例における術後ctDNA statusと再発について検討を行った。178例中14例(7.9%)に術後ctDNAが検出され(陽性)、陽性の14例中11例(78.6%)に再発が認められた。一方、術後ctDNA陰性では164例中16例(9.8%)で再発が認められた。術後のCEA測定では、再発を認めた27例中2例(7.4%)、再発を認めなかった151例中5例(3.3%)でCEAは上昇していた。術後ctDNA陽性例はいずれもCEAは上昇しなかった。術後ctDNA陽性例は、陰性例と比較してRFSが著しく減少しており(HR=18, p=2.6×10-12)、Kaplan-Meierによる3年RFS推定値はctDNA陽性例0%、陰性例90%であった。また、術後CEA上昇例は、非上昇例と同程度のRFSを示した(HR=1.6, p=0.5)。
臨床病理学的因子による再発リスク因子解析では、単変量解析においてT stage、切除リンパ節数、リンパ管侵襲の3因子が予後不良因子で、MMR statusはボーダーラインであった。臨床病理学的高リスク患者は低リスク患者よりもRFSが不良であった(HR=3.3, 95% CI: 1.6-7.0, p=0.002)。臨床病理学的因子に基づいた再発リスク分類にctDNA status を付加することで、臨床病理学的な低リスク群および高リスク群をさらに細分化して予後評価することができた。(低リスク: HR=28, p=9.2×10-8、高リスク: HR=7.5, p=0.0002)。多変量解析でも術後補助療法の有無に関わらず、術後ctDNA statusはRFSの独立した予後因子であった。36か月時点での再発予測に関するctDNA statusの感度、特異度はそれぞれ48%、100%であった。
術後補助化学療法によるctDNA statusへの影響を評価したところ、術後補助化学療法を3ヵ月以上受けた52例中6例(11%)は術後ctDNA陽性であり、陽性だった6例中5例は最初の術後補助化学療法の間に陰性に変化し、そのうち2例は術後補助化学療法完遂後に再び陽性になり、両例とも後に再発を認めた。一方、陽性から陰性に変化したままであった3例中2例は16ヵ月と34ヵ月時点で再発を認めなかった。術後補助化学療法完遂直後のctDNA陽性例は、RFS不良であった(HR=11, 95% CI: 1.8-68, p=0.001)。
なお、再発までのctDNAとCEA値を評価したところ、再発時点において、ctDNA陽性(評価可能27例中23例, 85%)は、CEA上昇(27例中11例, 41%)よりも高頻度で認められた(p=0.002)。また、ctDNA検出と再発との期間(中央値167日、IQR: 81-279)は、CEA上昇と放射線学的再発との期間(中央値61日、IQR: 0-207)より有意に長かった(p=0.04)。
以上のように、術後に採取された血液検体のctDNAにより、現在使用されている臨床病理学的因子よりも再発リスクが高い集団を特定できることが示された。ctDNAは術後補助化学療法の有効性をリアルタイムに追跡するバイオマーカーとなり、画像診断可能な明らかな再発巣が出現する前に治療を調整または変更できる可能性が期待される。
監訳者コメント:
ctDNA測定による高リスクstage II結腸癌の抽出
本論文はctDNAが体内の腫瘍遺残あるいは微小遠隔転移の存在を高感度に検出できるツールであるとして、臨床的有用性を検証している。検証事項は以下の2点である。第一に根治切除後にctDNAを測定し、術後ctDNA陽性例が実際に放射線画像診断による再発をきたすことを示すこと。第二にctDNA を定期的に測定し、腫瘍の遺残や再発の検出法として高感度であることを示すことである。その結果、同マーカーは腫瘍遺残を検出でき、術後補助療法の効果判定や再発の早期診断として有用であることを示した。
ctDNA statusは、従来の臨床病理学的な予後因子と相関がなく、独立した因子であったのは興味深い。同マーカーは臨床病理学的因子なリスクに関わらず、陽性例で術後再発をきたしていた。
術後補助療法非施行例では、ctDNA陽性例での再発率(陽性的中率)は78.6%と高値であり、再発の危険予測マーカーとして非常に有用である。しかし、36ヵ月時点での再発例に占めるctDNA陽性割合(感度)は48%であった。つまり、再発例のうち約半数は術後ctDNAが陰性であったことは注意が必要で、現時点での腫瘍遺残検出の限界を示すものである。予測マーカーとしての感度は十分とは言えないが、陽性的中率は高く、経時的な測定により、従来のCEA測定よりも術後補助療法の治療効果判定や早期の再発診断に有効であることが示唆される。
術後補助化学療法はR0切除が行われた症例に対して、腫瘍遺残や微小遠隔転移を制御し、予後を改善することが目標である。ctDNA は従来の方法では検出が行えなかった微小な腫瘍を検出でき、Stage II大腸癌の個別化治療に向けた有用なマーカーとなる可能性がある。
実臨床での使用には、大規模前向き試験での再現性の確認が求められる。
- 1) Edge S, et al.: AJCC Cancer Staging Manual. Springer, New York, 2010
- 2) Quah HM, et al.: Dis Colon Rectum. 51(6): 503-507, 2008[PubMed]
- 3) Niedzwiecki D, et al.: J Clin Oncol. 29(23): 3146-3152, 2011[PubMed]
- 4) Ribic CM, et al.: N Engl J Med. 349(3): 247-257, 2003[PubMed]
- 5) Sargent DJ, et al.: J Clin Oncol. 28(20): 3219-3226, 2010[PubMed]
- 6) Kopetz S, et al.: Oncologist. 20(2): 127-133, 2015[PubMed]
- 7) Venook AP, et al.: J Clin Oncol. 31(14): 1775-1781, 2013[PubMed]
- 8) Gray RG, et al.: J Clin Oncol. 29(35): 4611-4619, 2011[PubMed]
- 9) Zhang JX, et al.: Lancet Oncol. 14(13): 1295-1306, 2013[PubMed]
- 10) O'Connor ES, et al.: J Clin Oncol. 29(25): 3381-3388, 2011[PubMed]
- 11) Figueredo A, et al.: J Clin Oncol. 22(16): 3395-3407, 2004[PubMed]
- 12) Mamounas E, et al.: J Clin Oncol. 17(5): 1349-1355, 1999[PubMed]
- 13) Quasar Collaborative Group, et al.: Lancet. 370(9604): 2020-2029, 2007[PubMed]
- 14) Andre T, et al.: J Clin Oncol. 33(35): 4176-4187, 2015[PubMed]
- 15) Wood LD, et al.: Science. 318(5853): 1108-1113, 2007[PubMed]
- 16) Cancer Genome Atlas Network: Nature. 487(7407): 330-337, 2012[PubMed]
- 17) Diaz LA Jr, et al.: Nature. 486(7407): 537-540, 2012[PubMed]
- 18) Bettegowda C, et al.: Sci Transl Med. 6(224): 224ra24, 2014[PubMed]
- 19) Misale S, et al.: Nature. 486(7404): 532-536, 2012[PubMed]
- 20) Morelli MP, et al.: Ann Oncol. 26(4): 731-736, 2015[PubMed]
- 21) Diehl F, et al.: Nat Med. 14(9): 985-990, 2008[PubMed]
- 22) Tie J, et al.: Ann Oncol. 26(8): 1715-1722, 2015[PubMed]
- 23) Garcia-Murillas I, et al.: Sci Transl Med. 7(302): 302ra133, 2015[PubMed]
- 24) Sausen M, et al.: Nat Commun. 6: 7686, 2015[PubMed]
監訳・コメント:愛知県がんセンター中央病院 消化器外科部 医長 大城 泰平
GI cancer-net
消化器癌治療の広場