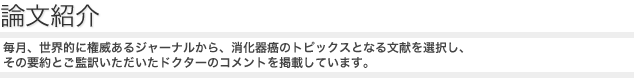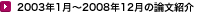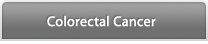監修:名古屋大学大学院 医学研究科 坂本純一(社会生命科学・教授)
進行胃癌および食道胃接合部癌に対するfirst-line治療としてのcetuximab+CPT-11+LV+5-FU療法:バイオマーカーを指標とした多施設共同第II相前向き試験
Moehler M et al., Ann Oncol. 2011; 22(6):1358-1366
近年、進行再発胃癌および食道胃接合部癌患者に対して多くの化学療法剤の有効性が報告され、治療方法も増えているが、予後は依然不良であり、より毒性が低く、有効で簡便なレジメンが求められている。さらに、胃癌の新しい治療戦略において新規の分子標的治療薬をいかに選択し組み合わせるかという問題はさらに重要であると考えられる。
進行再発胃癌および食道胃接合部癌治療ではCPT-11+LV+5-FU(IF)およびCPT-11+capecitabineレジメンが、CDDPベースのレジメンの有効な代替療法となりうることから、first-line治療としてcetuximab+IF療法の忍容性と有効性を評価する第II相オープンラベル非無作為化試験を実施した。本試験では腫瘍バイオマーカーが臨床転帰に与える影響についても解析した。
対象は、進行再発胃癌および食道胃接合部癌でECOG PS 0〜2、余命>12週の症例とした(緩和療法歴、術後または術前補助化学療法歴、放射線療法歴、モノクローナル抗体による治療歴、EGFR標的療法歴などを有する症例は除外)。
2006年8月〜2007年9月に登録された48例(男性34例、年齢中央値63歳)に対し、cetuximabは初回用量400 mg/m2に続いて250 mg/m2を週1回投与、CPT-11は80 mg/m2を2時間で静注、LVは葉酸ナトリウムとして200 mg/m2、5-FUは1,500 mg/m2をそれぞれ24時間で持続静注した(day 1、8、15、22、29、36)。治療は50日を1コースとし、忍容しがたい毒性またはPDを認めるか、患者が同意を撤回するまで継続した。
主要評価項目はRECIST基準による奏効率(ORR)、副次評価項目はPFSおよび1年生存率とした。バイオマーカーについては、KRAS、BRAF、PIK3CA遺伝子の変異解析、およびEGFR1、VEGF-C、VEGF-D、VEGFR3、HER2、SMAD4、PTENの蛋白発現状況解析を実施した。
有効性として、ORR 46%(95%CI 31-61%)、SD 33%、病勢コントロール率79%、病勢コントロール期間は21週であった。追跡期間は31.2ヵ月(範囲5.7-34.8ヵ月)、PFSは9.0ヵ月(95%CI 7.1-15.6ヵ月)、OSは16.5ヵ月(95%CI 11.7-30.1ヵ月)であった。OSおよびPFSを奏効状態別に解析すると、CRまたはPR群はSDまたはPD群と比較してOS(平均19.1 vs 12ヵ月、p=0.001)、PFS(平均10.6 vs 6.0ヵ月、p=0.041)ともに延長していた。また病勢コントロール率別に解析してもCR、PR、SD群の方がPD群より優れていた(OSは平均18.1 vs 4.5ヵ月、p=0.001、PFSは平均10.0 vs 1ヵ月、p=0.001)。
バイオマーカー解析において、遺伝子変異の評価可能症例は34例であった。そのうち3例にKRAS変異が認められ、うち2例は治療中に奏効を示した(CRとPRが1例ずつ)が、試験終了時には3例全例がPDとなった。BRAF変異は4例で認められ、全例がCR+PR+SD群であった。PIK3CA変異は2例で認められ、試験終了時にはPDとなった。複数の変異を有する症例は認められなかった。
EGFRは39例中26例(67%)で発現していた。奏効状態別にみると、SD+PD群に比べCR+PR群で発現頻度が高かった(50% vs 84%、p=0.041)。EGFRの発現が強度であった12例では腫瘍反応性との関連はさらに顕著(p=0.006)であったが、逆に発現していなかった13例のうち奏効が認められたのは3例(23%)のみであった。しかし、EGFR発現(強力な発現も含め)とOS(log-rank検定のp=0.567)、PFS(log-rank検定のp=0.663)との間に有意な関連は認められなかった。
PTENは34例中7例(21%)で発現していた。PTEN発現例では、SD+PDを示す例(1例)よりも奏効を示す例(6例)が多く、OS(発現群 平均23.8 vs 非発現群 平均14.3ヵ月、p=0.0127)およびPFS(14.0 vs 6.8ヵ月、p=0.035)延長に有意に関連していた。
グレード3/4の副作用で最も多かったものは下痢(15%)、皮膚毒性(8%)および感染(8%)であった。発疹(全グレード)は58%に認められたが、発疹の出なかった群と比べて腫瘍反応性およびOSに有意差は認められなかった。
以上のように、cetuximab+IFは忍容性に優れ、有効性データも期待できるものであることが示された。Cetuximab投与に関連した発疹の臨床成績に対する役割は本試験では明らかにできなかったが、進行胃癌において、cetuximabと化学療法とを併用し、選択したバイオマーカーにより予後を予測する第III相試験(EXPAND試験)が現在実施中である。
胃癌に対する分子標的治療薬
現在までに施行された進行・再発胃癌に対する分子標的治療薬の臨床試験には、VEGFを標的としたbevacizumab+CPT-11/CDDP、EGFRを標的としたcetuximab+L-OHP/5-FU/LV、HER2陽性胃癌に対してtrastuzumabを用いるToGA試験などがある。Cetuximab+CPT-11/5-FU/LVに関しては、2007年にPintoがdoseは異なるものの38例の検討で、ほぼ同等の結果(ORR 44.1%、time to progression 8ヵ月)を報告している。Pintoらのレジメンではrashが81.6%に認められ、21.1%の症例ではグレード3/4が記録され、また嘔吐や下痢をはじめとする消化器症状もそれぞれ半数に発現している。
本試験では5-FU/LVは若干増量しているもののCPT-11の1回投与量を180 mg/m2から80 mg/m2に減量し、副作用発現率を半減させたことは本レジメンの有効性を示したものである。治療に難渋する副作用の一つである皮膚毒性に対して積極的にプロトコールを導入した事も副作用軽減に寄与したものと考える。
バイオマーカー解析では、EGFR、PTENにおいて有用性が示された。分子標的治療は高価であるとともに有害事象の発現も軽視することができず、胃癌に対する有効な個別化治療のために、種々の分子標的治療薬と化学療法剤を組み合わせた、さらに安全で高い奏効率を示す可能性のあるレジメンを検証する臨床試験の結果が待たれる。
監訳・コメント:名古屋市立大学大学院 木村 昌弘(消化器外科学・准教授)
GI cancer-net
消化器癌治療の広場