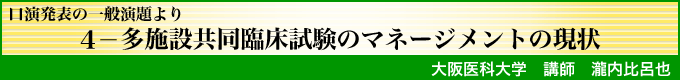 |
| O-118は日米における臨床試験における現場でのシステムの違いについての口演であった。
O-118: |
一方、MSKCCは、1884年にニューヨーク州立病院を基礎として設立された合衆国初の癌センター病院である。ニューヨーク州マンハッタン東のメディカル・センターに位置し、病床数は425床と、駒込病院の約半分であるが、Clinical Trial Serviceという治験専門の事務局がある。1999年〜2001年の駒込病院の治験事務局とMSKCCのClinical Trial Serviceを比較してみた。駒込病院の治験事務局のスタッフ数が6人、全臨床試験数35、胃癌の臨床試験数が5であったのに対し、Clinical Trial Serviceのスタッフ数は45人と多く、全臨床試験数 約400、胃癌の臨床試験数は15であった。また、治験事務局の症例数が501、適格例101例、うち臨床試験への参加同意が得られたのは86例(85%)であったのに対し、MSKCCでは、症例数362、適格例205例、うち臨床試験への参加同意が得られたのは201例(98%)であった。MSKCCでは、ほとんどが手術当日に入院してくるということもあるが、外来診療時間内に担当医師、CRC、research nurse (RN) 同席のもとで、患者本人・家族に説明を行なっている。また、Cancer Information Serviceが、常時患者対応にあたり、医療者とのスムーズなコミュニケーションを可能にしている。それとあわせ、インターネット、Physician Data Query(PDQ)などを活用し、臨床試験に対する意識の向上をはかる取り組みも行なっている。MSKCCでは、臨床試験においての医師、CRC、RNなどの分業がはっきりなされていた。また、それ以外にも、一般的に米国の患者さんは臨床試験に関する意識が強く、「この病院に行けば臨床試験を受けられ、医療費がタダになる」といった情報交換も活発なようである。 駒込病院における臨床試験の対象例では、告知および治療についての説明が長時間を要し、かつ勤務時間外に及ぶことが多く、医師の負担が大きいと言える。また本邦における臨床試験の発展のためには、社会的な啓蒙とCRCなどの専門スタッフの充実が必要である。 |
