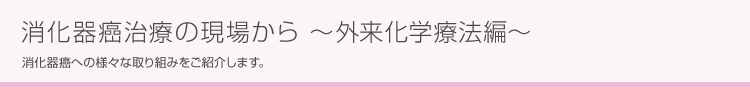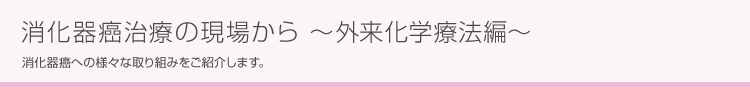Q. センターで取り組まれているリスクマネジメントについてお聞かせください。
A:
・レジメ管理
電子カルテでの管理と各診療科の連携が特徴です。当院では、レジメは、各診療科が電子カルテ上で登録したものをその診療科だけが使用できる仕組みになっているため、他診療科で登録されたレジメに適応のある患者さんがいても、その診療科で未登録だと使用できません。レジメは化学療法部と薬剤部が中心になって統括管理し、各診療科の抗癌剤担当医師とやりとりをしています。また、基本的に新規レジメは院内のIRBないしレジメ審査委員会で検討されることになっています。
・主治医とセンター専任医師によるダブル・チェック体制
治療時のインフォームドコンセント(IC)についても電子カルテ上で管理されています。診療科別にまず1回、患者さんへの治療等の情報提供を行い、ICをとります。さらにセンターでも改めて情報提供をしてICをとるというダブル体制が可能です。患者さんにとっては医学専門用語などで難解な説明もありますが、幸いスタッフが充実しているため、二度にわたって詳細な説明ができることが事故の予防につながっていると思います。
・前処置薬も含めた薬歴管理
一方、誤投与を防ぐための薬歴管理として前回治療時の処方を振り返るのですが、インターバル、用量などに加えて、当院では患者さんごとに処方の違いが出やすい前処置薬についても把握します。週1回、センター専任医師、看護師、薬剤師でカンファレンスを行い、疑義照会、件数などを挙げて検討し、インシデントとなる事例については医療安全部に報告します。
Q. センターで行う化学療法のなかでも件数が多い消化器癌治療についてお教えください。
A: センターで行う化学療法の約半数を消化器外科が占めています(図2)。消化器癌は、もともとの患者数が多いことと、最近では術後化学療法を積極的に行うようになっていることも増加の一因と思われます。使用レジメは、切除不能・再発大腸癌症例では、FOLFOXかFOLFIRIを中心に行っています。化学療法を開始する際のCVポート埋設時のみ1泊程度入院していただくほかは、最近では初回投与から外来で行います。FOLFOX
4では、その後、2日目、3日目も連続して通院していただきます。一方、mFOLFOX 6では2日目は自宅で、3日目に再通院です。これを2週間ごとに最低でも4クール繰り返します。抜針は近隣の病院へお願いすることもありますが、基本的には来院をしていただき、センターで抜針します。外来治療主体の患者さんは特に長期の治療スケジュールを正しく把握しておいていただく必要があるため、医療関係者用とは別の患者さん用のクリニカルパスとスケジュール表をお渡しします(図3)。また、自宅で記入する副作用チェック表も渡しています。
図2 円グラフ 臓器別のべ患者数

図3 クリニカルパスとスケジュール
 |
|
クリニカルパス(ダウンロード用) |
|
 |
 |
|
スケジュール表(ダウンロード用) |
|
永田先生は手製のスケジュール表を患者さんごとに作成し、3部コピーして患者さんに1部、主治医のカルテに1部、センターのカルテに1部挟み込んでいる。これだけはすぐに目にできるよう、電子カルテにはあえて組み込まない工夫をしている。
Q. センター内外のスタッフへの教育や、理解を深めるための試みはありますか?
A: センターのスタッフはカンファレンスを通し、コミュニケーションや知識を深めています。
また、その他、癌治療に関する病職員への教育を目的としたセミナーを、1ヵ月に1回開催しています。抗癌剤の作用機序から緩和ケア、地域連携、チーム医療まで毎回テーマを変えて、1年間ですべてのテーマを網羅できるように構成しており、多いときで230名ほど集まったこともあります。