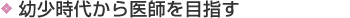
親戚に医師や歯科医、薬剤師がおり、亡くなった母の希望もあって、何となく子供の時から医師になることを目指していましたが、中学、高校と楽しい思い出ばかりで猛勉強した記憶はあまりありません。普通のサラリーマンだった父が国立の大学しか認めなかったため、ちょうど医学部が6年制になった最初の年(1955年)に千葉大学を受験しました。当時の千葉大周辺は農村地帯で何もなく、大学の立派な建物と、周辺の長閑さのギャップに驚いたことを覚えています。
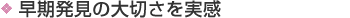
大学1年生の時、千葉県富里の無医村地帯で、教会を借りて地域住民の健診を行っていた日本キリスト者医科連盟の活動にボランティアとして参加しました。この活動は野村実先生や日野原重明先生が中心となって行われていました。そのとき、何気なく胸のX線写真を仲間の技師に撮影してもらったところ、早期の結核であることが判明しました。種々の検査の結果、感染の危険性はないと判断されたため、その後も学生寮にとどまり学業を続けることができましたが、もしこの偶然の発見がなかったら数年間の療養生活を余儀なくされていたことでしょう。後に白壁彦夫先生や市川平三郎先生から「早期発見」の大切さを厳しく教えられましたが、自分自身の経験からも、「早期発見」はその後の診断における自分の信条となりました。

当時の千葉大学では、中山恒明先生が教授をなさっていた第二外科教室が有名でした。学生時代に中山先生の臨床講義を受け感銘を覚えましたが、手先が不器用なこと、体力的にも不安があったことから自分は外科には向かないと思っていた頃、胃の放射線診断の大家、熊倉賢二先生との出会いがありました。熊倉先生の診断に対する信頼度は絶大で、外科の先生方も一目置いていました。また、当時講師をされていた白壁彦夫先生の評判も方々から耳にしており、自分の進むべき道は「これだ!」と思い診断の道に進みました。もともと癌専門医になりたかったので、診断を究め、病態に精通した医師として癌治療に関わろうと思ったのです。
教室では先輩医師とともに、フィルムの交換、撮影、現像、読影、機器の整備など、すべてを自分たちで行いました。朝9時半頃から夕方4時頃まで、休みなしにレントゲン室にこもりっきりで、1日に200枚近くこなすこともありました。しかし、この時の経験はその後の実臨床に非常に役立ち、どこの施設でも、どのような症例でも撮影できる技術が身に付きました。

国立がんセンターの放射線診断部で実務に携わったのですが、この時の国立がんセンターは、初代院長であった久留勝先生の下、石川七郎先生、木村禧代二先生、末松恵一先生、三輪潔先生や仁井谷久暢先生、藤田浩先生など、後に癌治療領域の中心となる錚々たる顔ぶれが集結しており、癌を克服したいという熱意と気概が溢れていました。
久留先生は亡くなった患者さんは必ず解剖して、「遺体に教えていただく」という考えを貫く方でした。私が胃病変をX線で良性と診断し、内視鏡医や執刀医と意見が食い違ったときなど、皆で固唾を飲んで病理結果を見つめたことがありましたが、自分の判断が正しかったことが2度続けてあった時は、久留先生から「君の診断は大したものだ」とお褒めの言葉をいただきました。そうした刺激的な環境で約2年半勤務した後、順天堂大学消化器内科の白壁教授の下に異動しました。
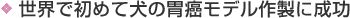
白壁先生の指導は今でいうOJT(on the job training)であり、とにかく自分の目で見て、自分の手で触り、確認することを重視したものでした。まだまだ手術が癌治療の中心という時代に、外科医に対して診断の専門家として治療法を助言したり、病態について意見を述べられたりしていました。
また、この時期にイヌに転移を有する胃癌モデルを作ることに成功しました。当時はラットやマウスの癌モデルしかなく、大型動物に人間と似た癌種を発現させることが課題となっていました。他のグループはメチル基ニトロソグアシジン(NG)を使って実験をしていたのですが、生化学で得た知識を基に、直接接触させることで、世界で初めて犬の胃癌モデルを作ることができたのです。真夜中に発癌経過をX線撮影することなど、寝る間も惜しんで実験に励んでいました。
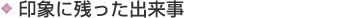
1972年、木村禧代二先生を中心として東京癌化学療法研究会が発足し、その共同研究第1号としてtegafur(FT)の臨床試験を行いました。まだ化学療法の効果が確立していない時代でしたが、PhaseⅠ/Ⅱ試験で、肝癌症例への投与を試みました。 この患者さんは外見からも明らかに腫大していることが判別でき、シンチグラムの結果でも多発病変が確認された進行癌でした。周囲が疑問視する中、FTを投与したところ、どんどん腫瘍が縮小したのです。その結果は周囲の医師だけでなく、看護師やその家族も癌は誤診だったのではないかと疑うほど素晴らしいもので、結局その患者さんはあと3ヵ月で3年の生存をされました。これは経口癌化学療法の有効性が認められる第一歩だったと思っています。その後も多くの素晴らしい新薬の誕生に立ち会ってきましたが、私にとっては一番最初のこの薬剤、この症例が最も印象深く記憶に残っています。
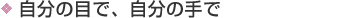
今日、癌治療は専門化が進んでいます。専門分野に詳しくなることは決して悪いことではありませんが、ここからここは何科と細分化することなく、患者さんの状態をトータルで捉えて、その中でそれぞれの専門性が考慮される治療の実現を望みます。検査技術や機械の進歩、情報が広く入手できるなどは医師にとっても患者にとっても非常に良いことですが、検査数値だけで患者さんの診断や効果をみたりせず、患者さんの訴えを聞き、状態を自分の目で見て、身体に触れ、そして診断をして欲しいと思います。
私は診断を究め、病態に精通することで、癌治療に関わろうと思いましたし、教育面も心掛けてきました。結果的には化学療法にも深く携わることになりましたが、決して最初から化学療法のプロを目指したわけではありません。若い先生方は、2006年の第44回日本癌治療学会総会で会長の赤座英之先生がおっしゃっていたように、“medical oncologist”ではなく“medical scientist”を目指して欲しいと思います。
|